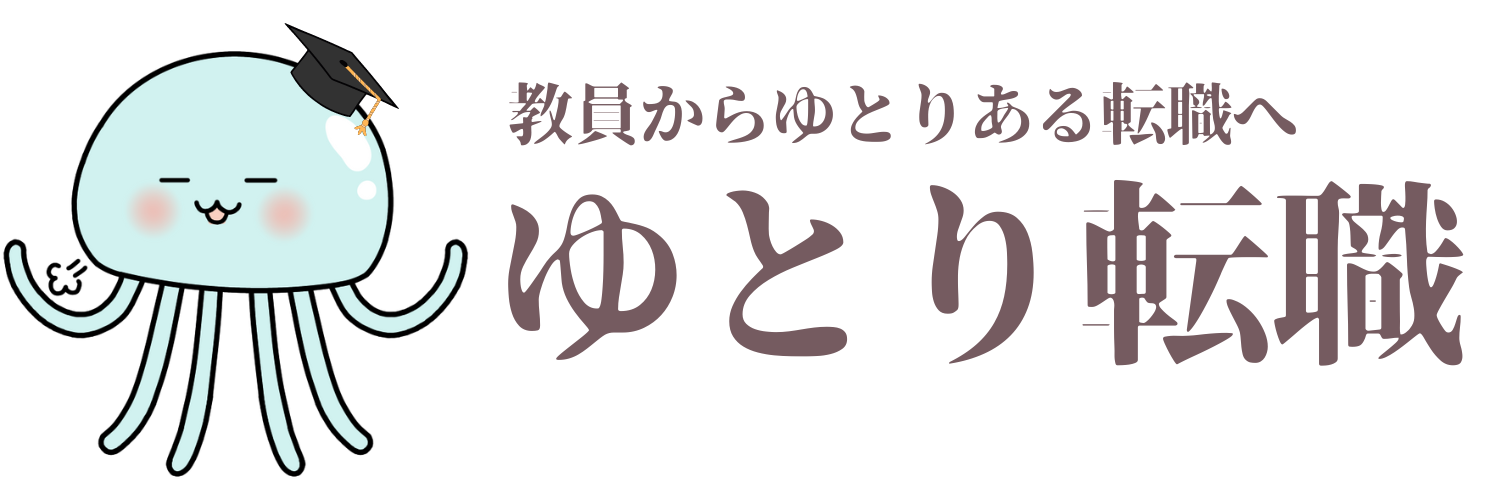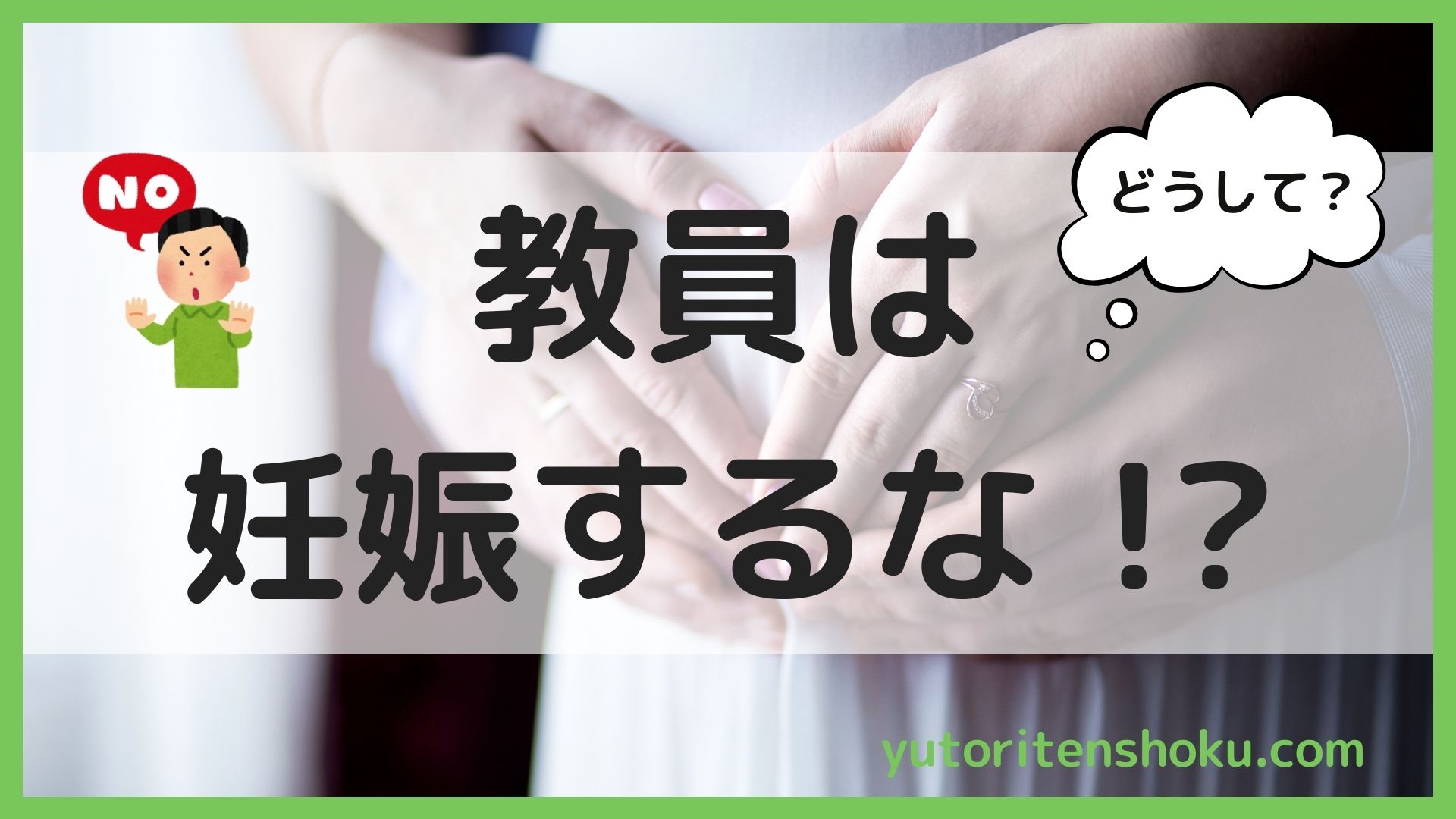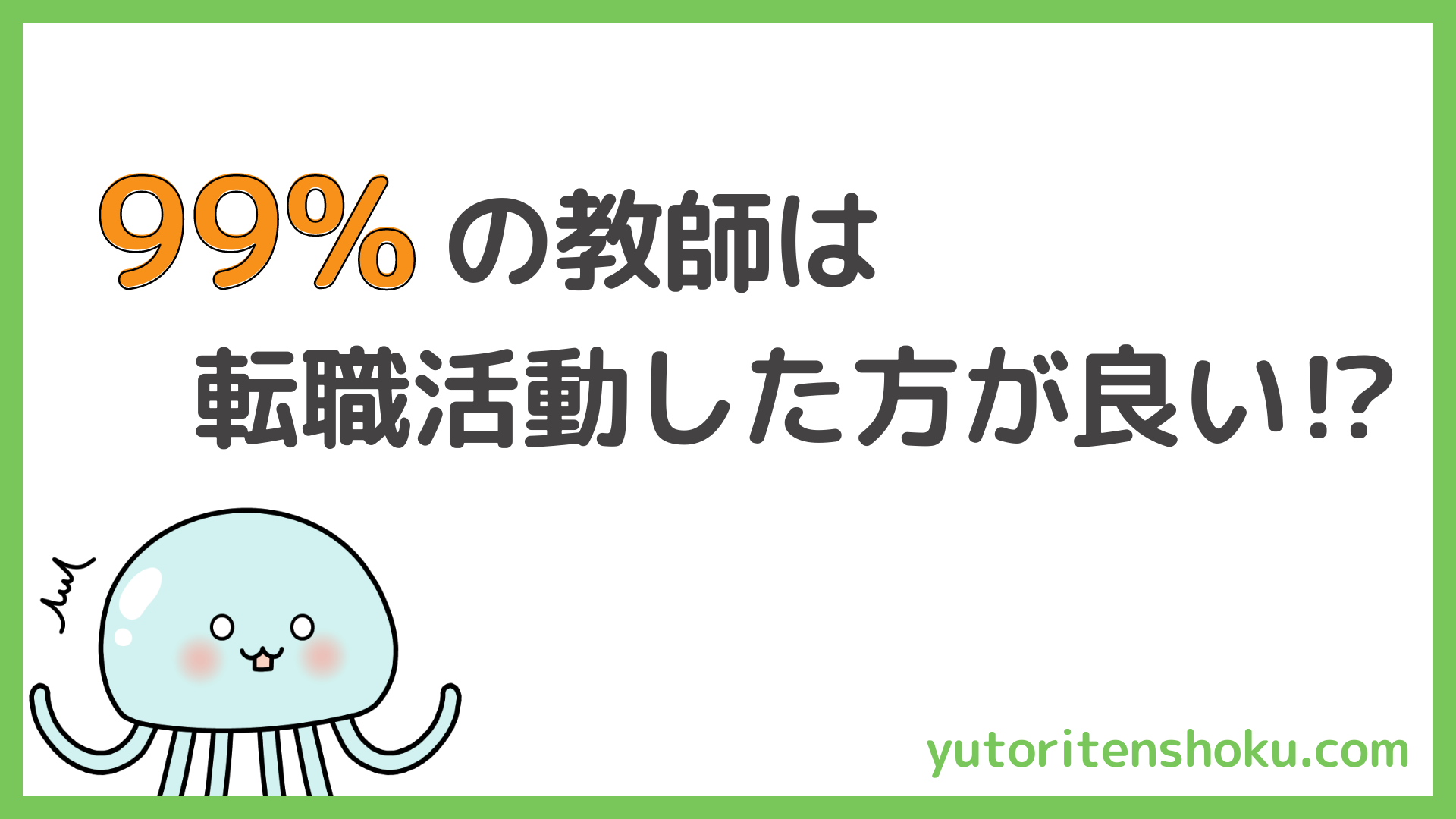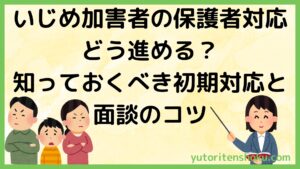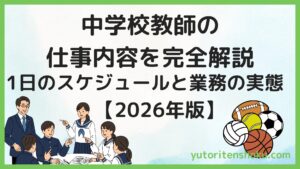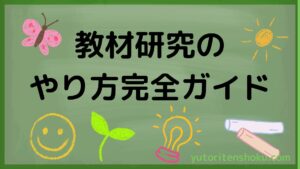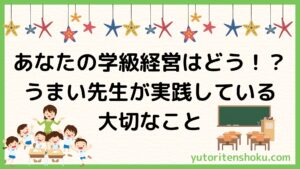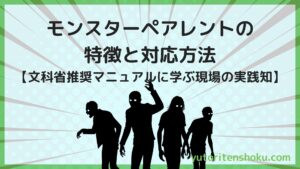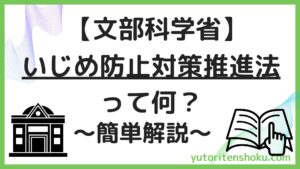ゆとり
ゆとり教員って妊娠しちゃダメなの?




妊娠しにくい職場の雰囲気を感じるなぁ…
教員として働く女性の方の中にも、上記のように「妊娠したいのに、しづらい」と感じている方も多いのではないでしょうか?
実際、近年の教員不足により学校現場ではどんどん仕事が溢れていて、簡単に休むことができない雰囲気を感じるようになってきていますよね。
「周りの先生に迷惑かけたらどうしよう」「今の子供たちはどうなるの?」などと、次から次へと不安が募り、なかなか妊娠に踏み切れない人も多いはずです。
そこで、今回は教員の妊娠が難しい背景にある制度や職場の問題を解説し、実際の声をもとに教員の妊娠にまつわるリアルな実情を徹底解説していきます。
- 「教員は妊娠するな」と言われる理由
- 教員の産休・育休制度の現実
- 妊娠のベストタイミング
- 妊娠報告のタイミングと順番
- 教員の妊娠に対するクレーム対応
- 妊娠・出産と教職を両立するための工夫
教員に「妊娠するな」という空気は本当にある?
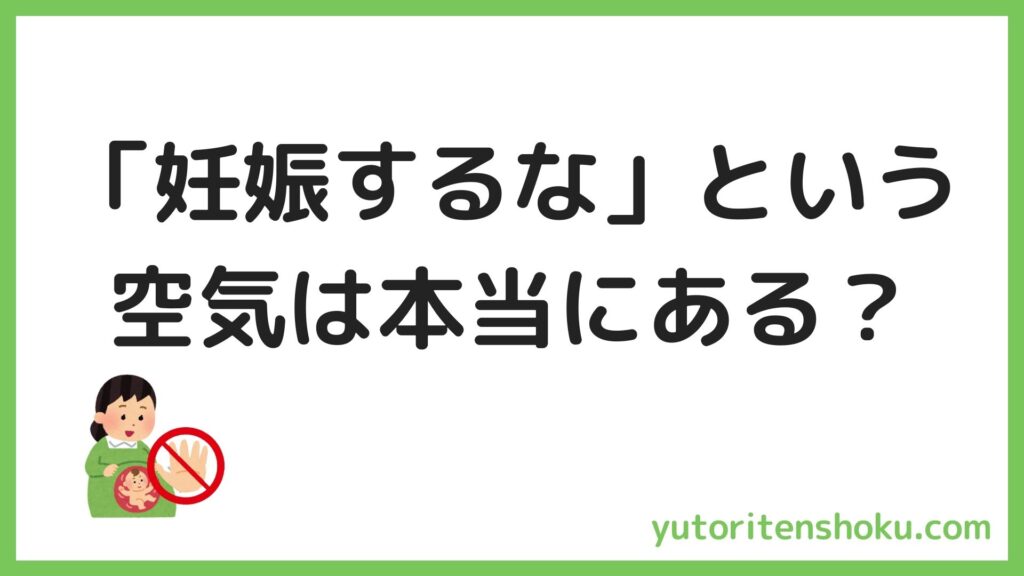
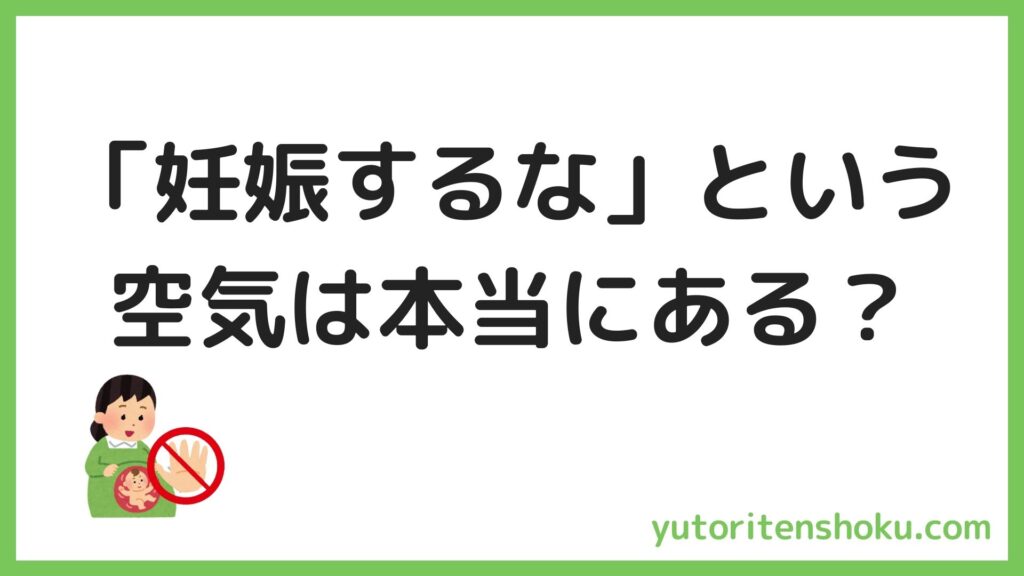
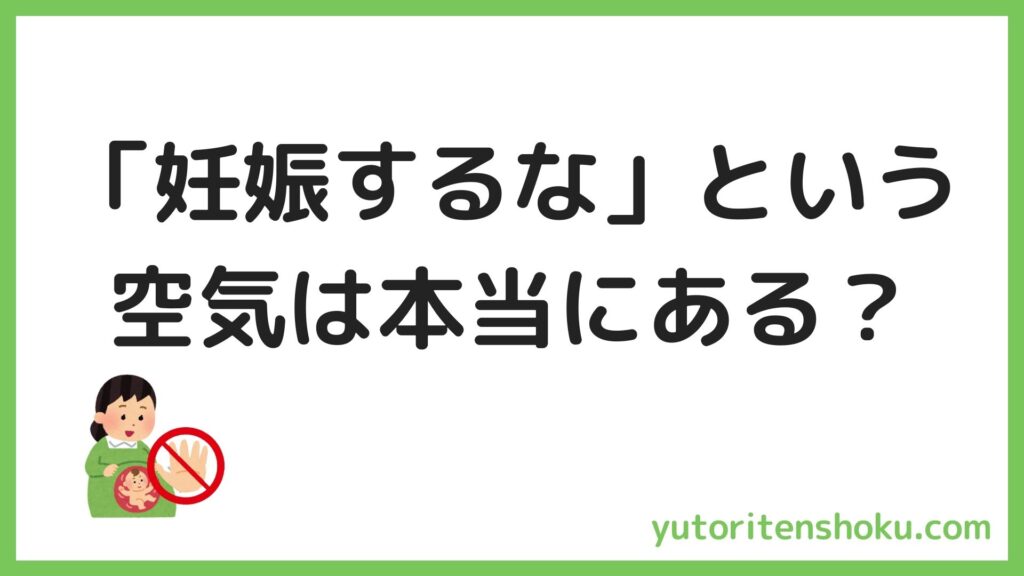
SNSに溢れるリアルな声
妊娠は本来自然なライフイベントであり、誰もが祝福されるべき出来事のはず。
しかし、教育現場ではそれが“自己中心的”と受け止められてしまい、SNS上にはたくさんの教員の悲鳴の声が上がっています。
この他の教員の投稿にも、「うちの学校でも似たようなことがあった」という反応が多く見られ、特定の職場だけで起こっている問題ではないことがうかがえます。
こうしたことから、現在の学校現場では「妊娠する=迷惑なこと」という潜在意識が根付いてしまっているのかもしれません。
この空気の背景にある学校現場の事情
このような背景には、以下のような学校現場の問題があります。
- 慢性的な教員不足
- 代替教員の確保が困難
全日本教職員組合によると、34都道府県11政令市で、合計4739人の教員未配置が起きていることが明らかになりました。
特に担任を持つ教員が産休に入ると、学級運営の引き継ぎや保護者対応の負担が他の教員にかかりやすくなり、代替教員の確保が必要になります。
しかし、上記のデータのように教員の穴が埋まらないという過酷な現状があちこちで生じているため、「妊娠したくてもしづらい」という雰囲気が学校現場には存在しているのです。




私のいた学校でも、代替教員が見つからず、大変だったよ…
制度はあるのに使えない?教員の産休・育休の現実
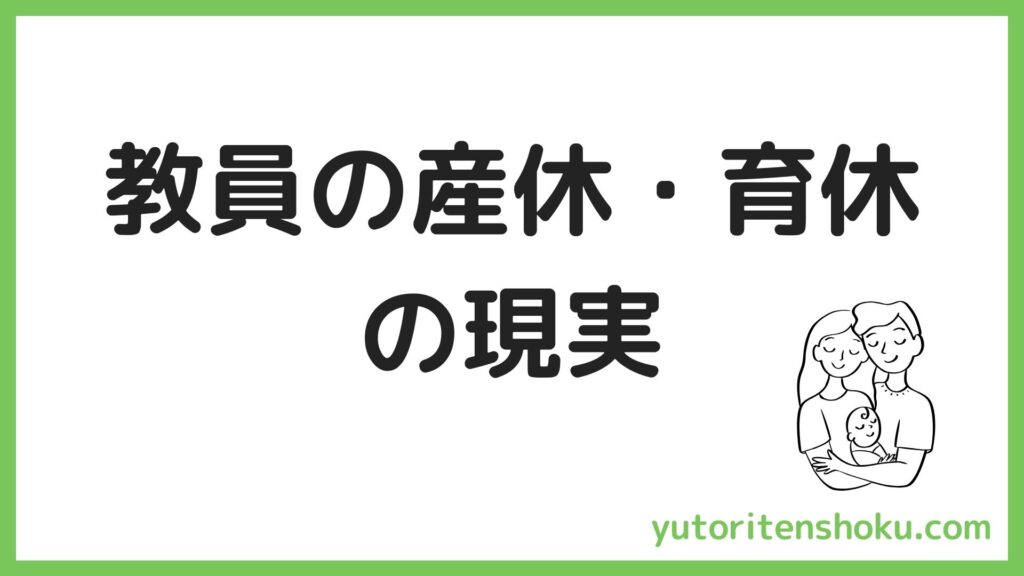
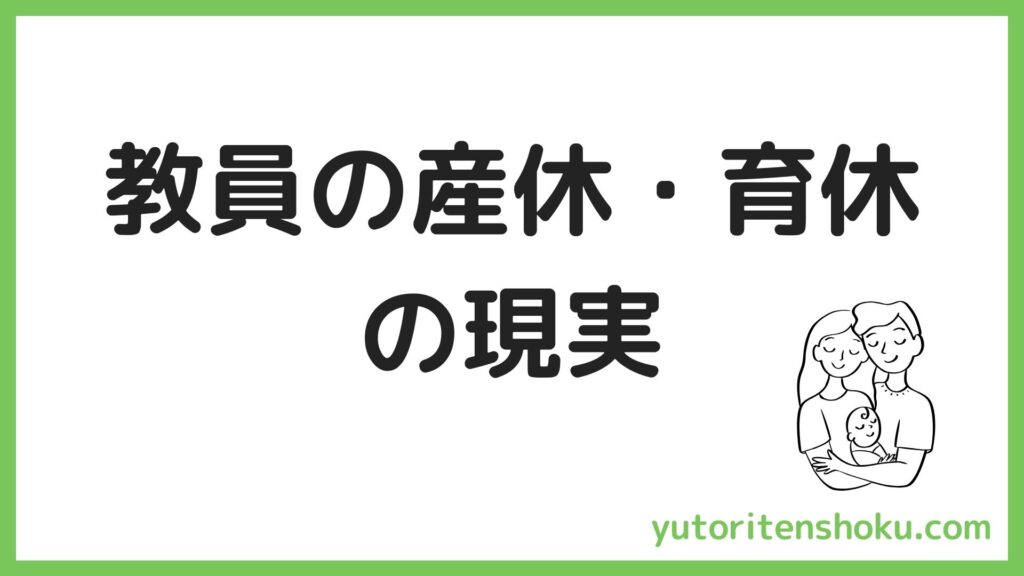
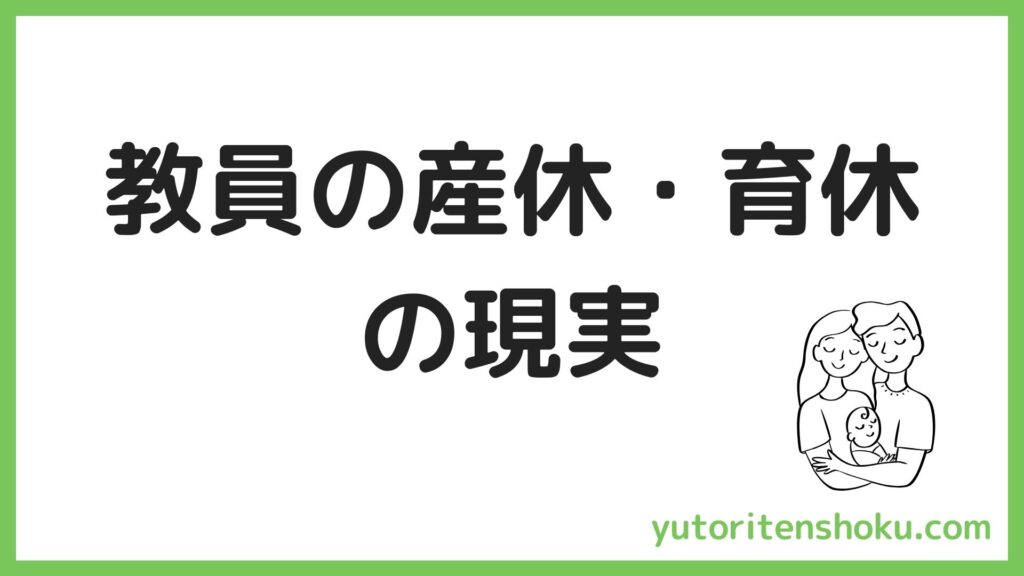
教員が使える産休・育休制度とは
公立学校の教員は、以下のような産休・育休制度が整備されています。
- 産前産後休暇
- 育児休業
産前産後休暇
出産予定日前の8週間~予定日後の8週間に産前産後休暇が取得できます。
ただし、予定日よりも早く生まれた場合は、その生まれた日から8週間後になります。
育児休暇
教員の育休期間は子どもが最大3歳になるまで取得することができます。




教員の産休や育休制度は充実してるけど…
産休・育休について詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください!↓
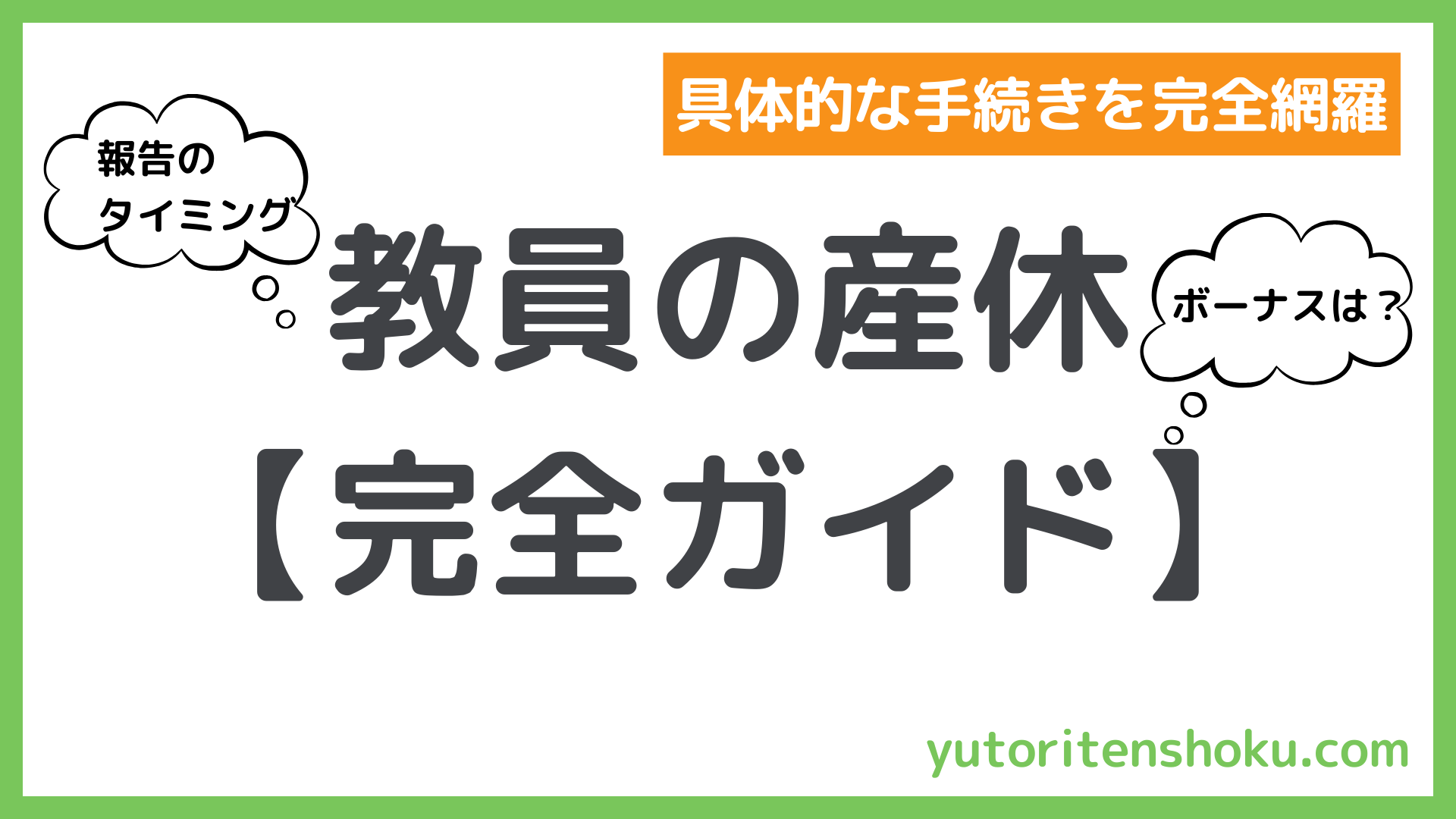
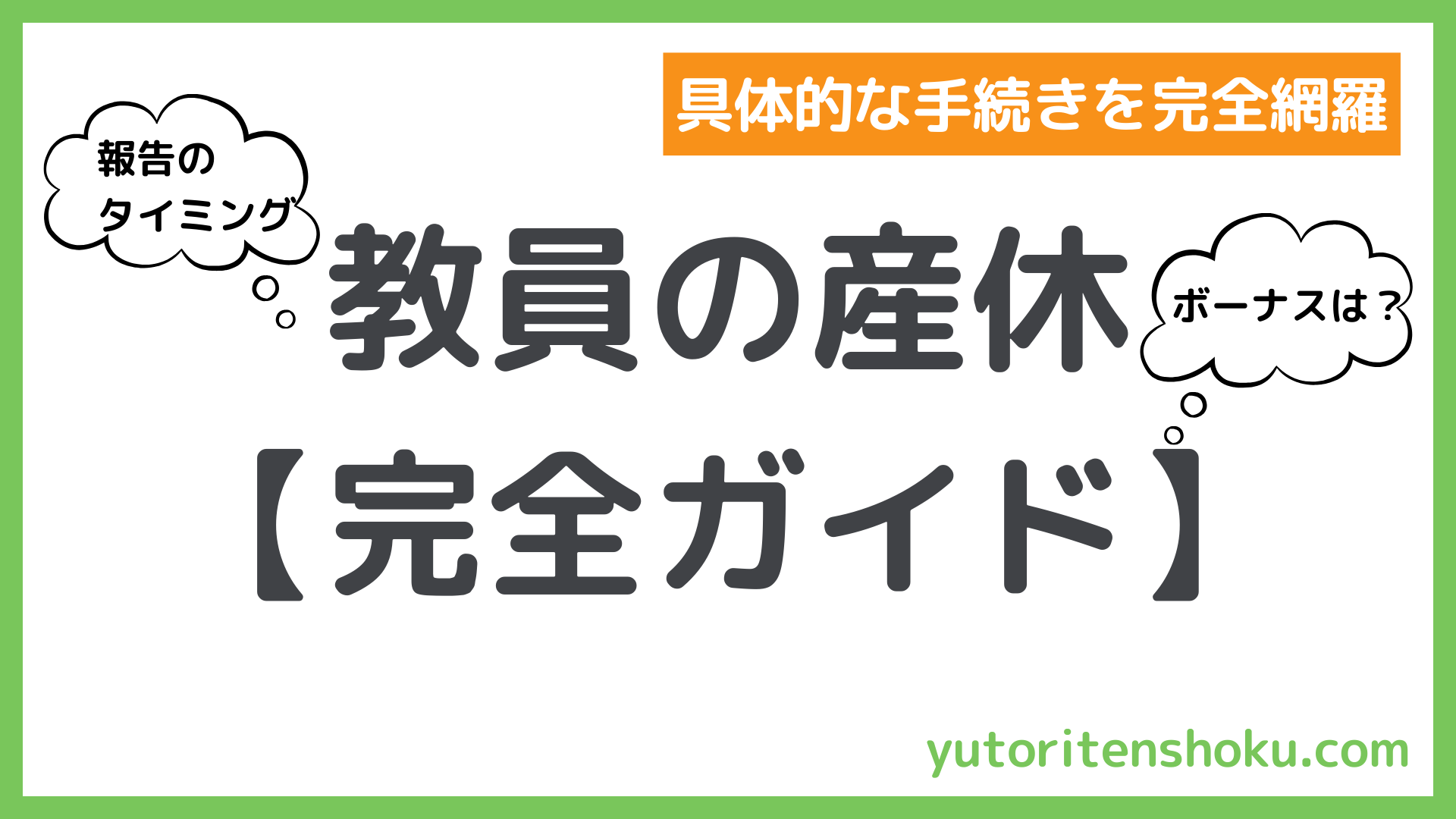
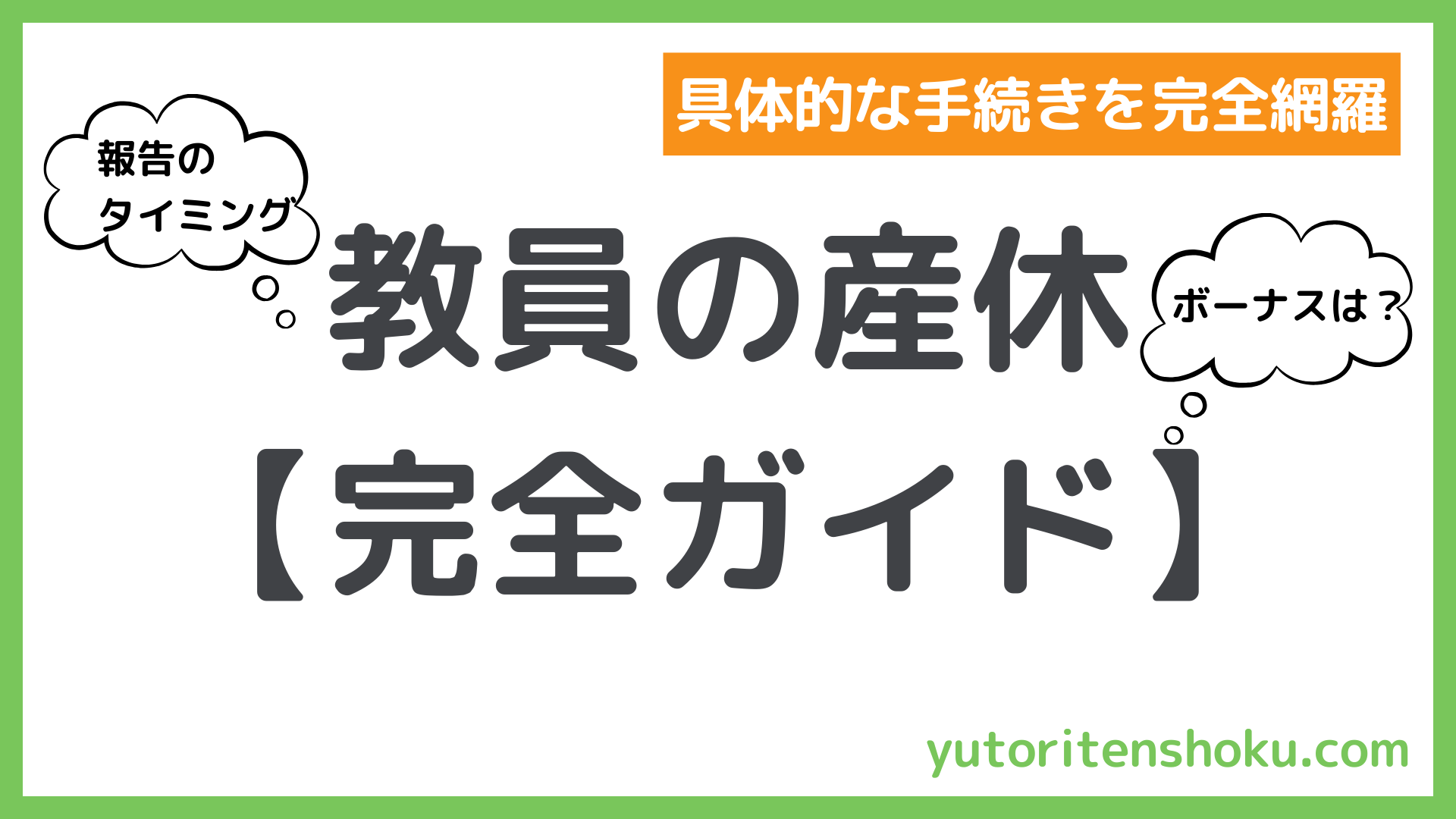
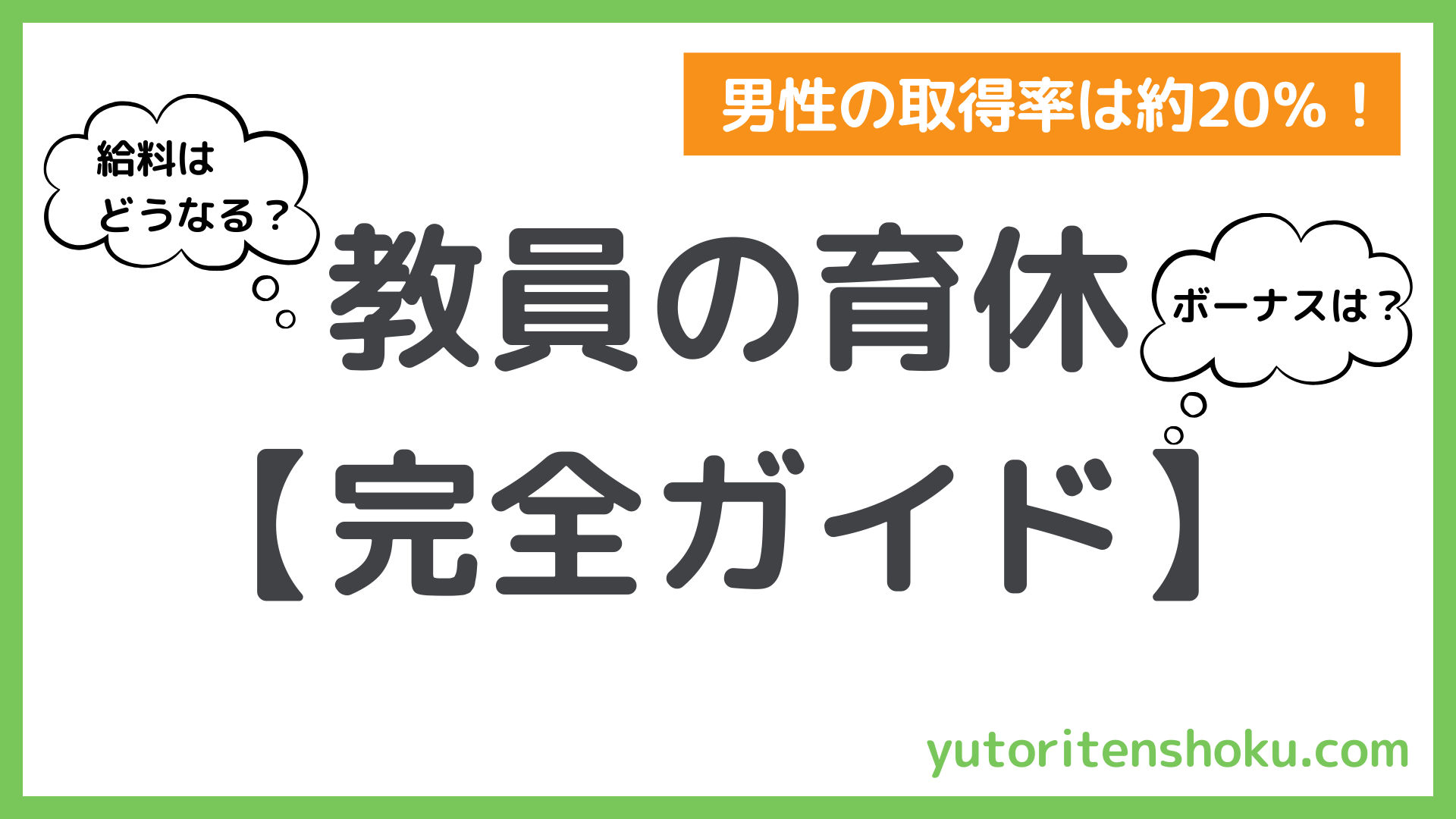
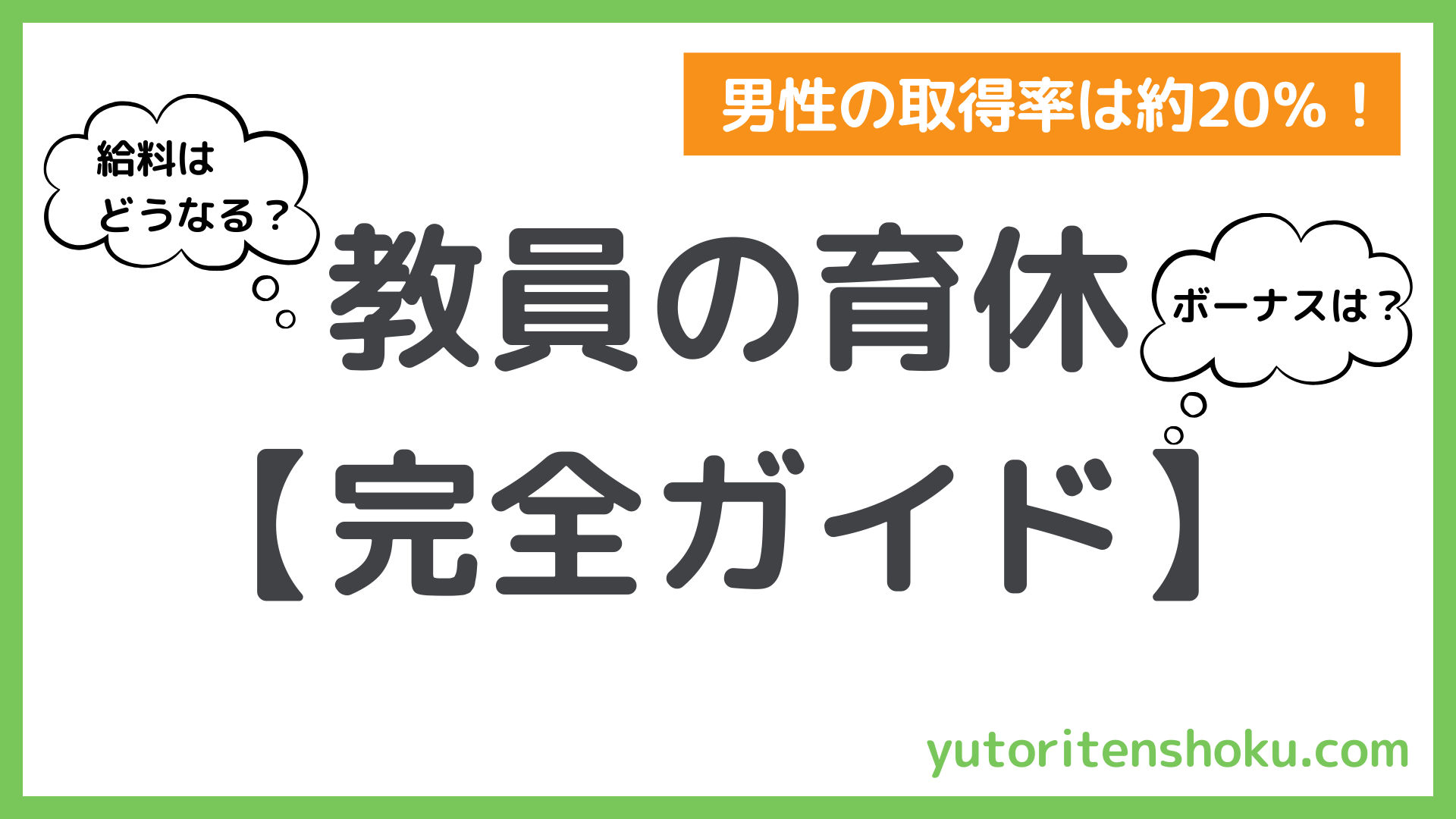
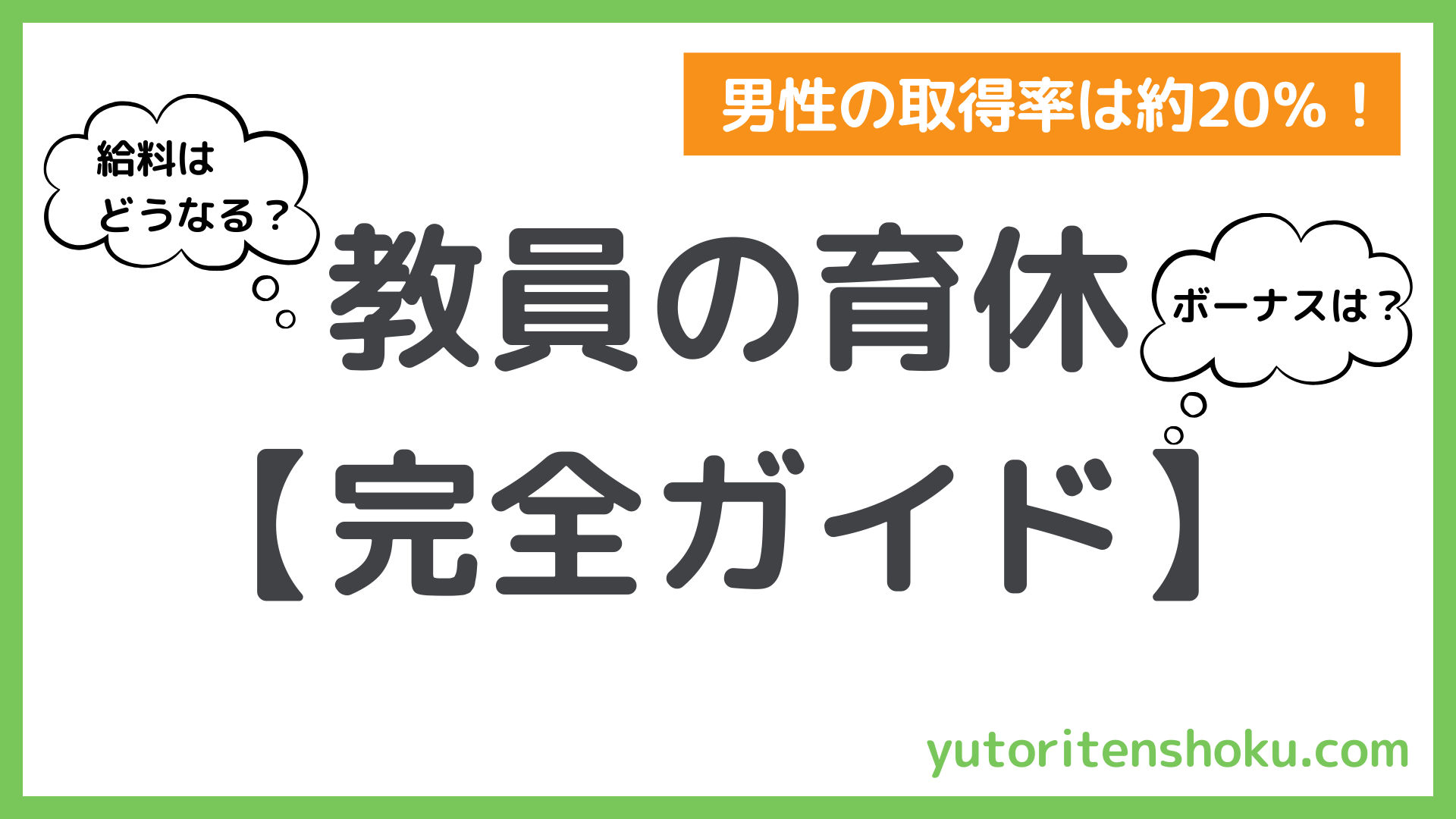
制度の利用状況と課題【データあり】
文部科学省の調査によると、令和3年度の育児休業取得率は以下のようです。
- 男性職員 9.3%
- 女性職員 97.4%
この結果から、女性教員の育児休業取得率は高い水準にありますが、男性教員の取得率は依然として1割未満であることが分かります。
このようなSNSの声の通り、制度があっても現場に理解がない、代替要員がいないといった理由で、十分に活用されていないのが実情です。
妊娠するタイミングはいつがベスト?
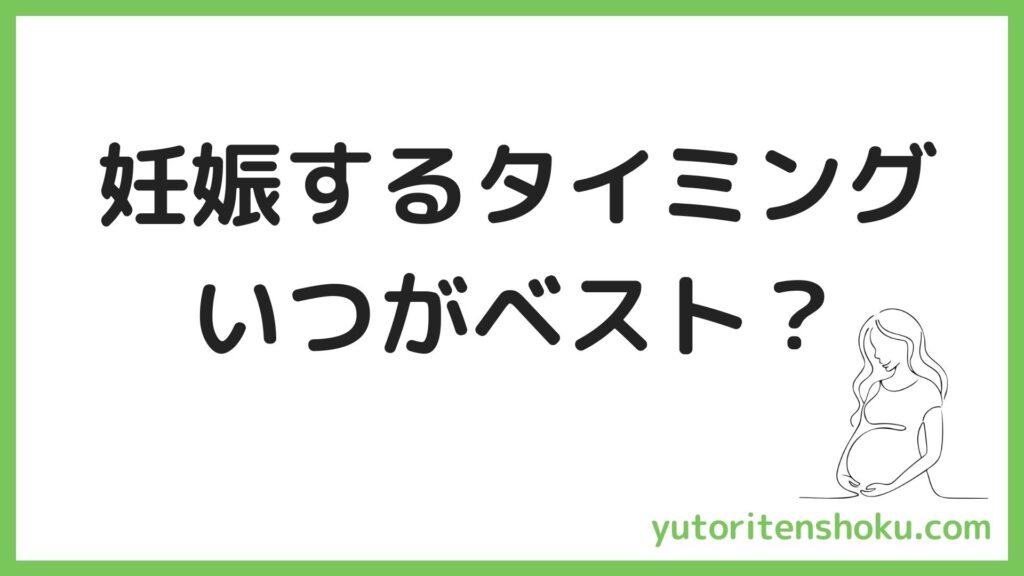
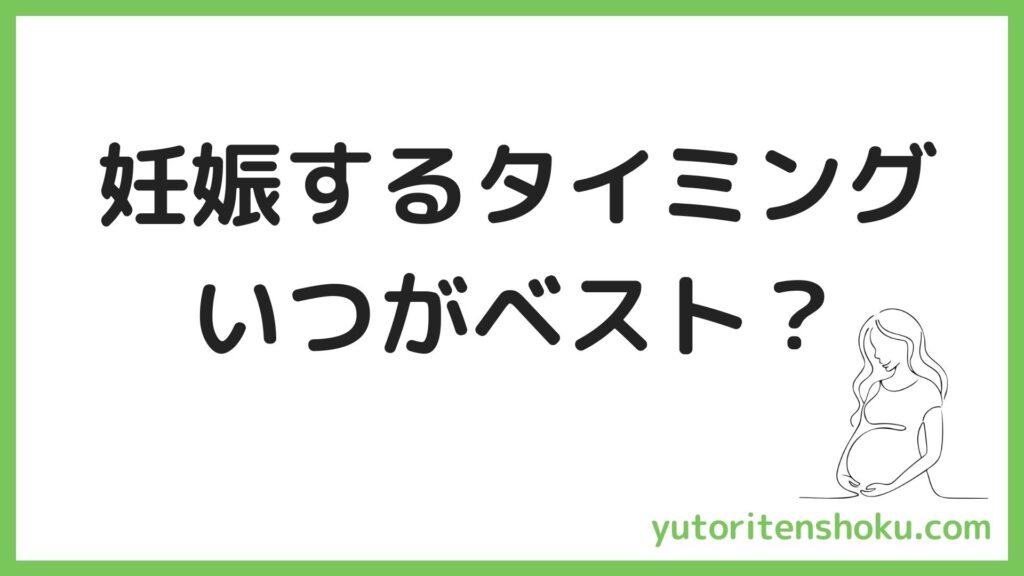
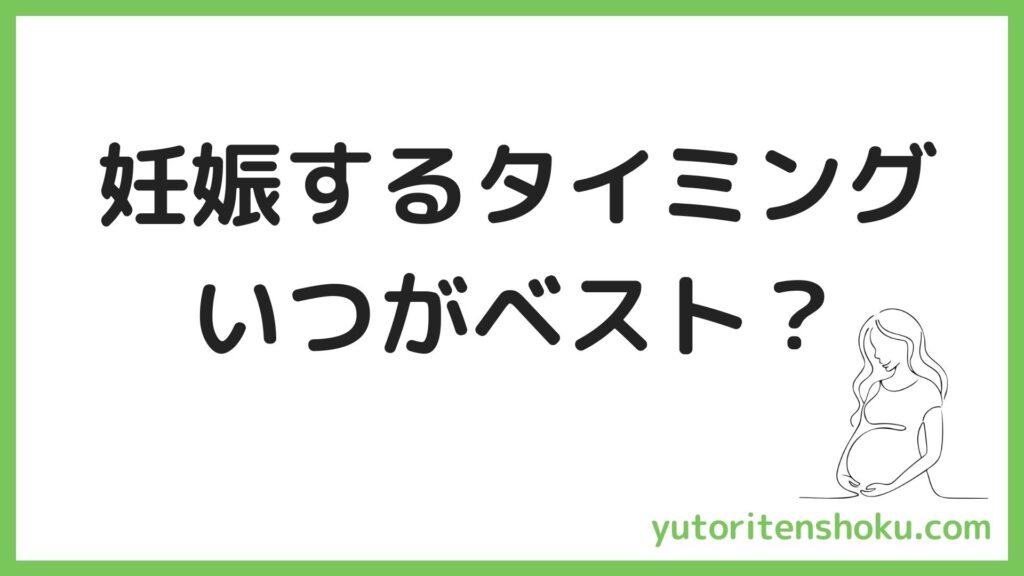
教員は妊娠しづらいという雰囲気があるのは事実。とはいえ、やっぱり大切な人との子供は授かりたいですよね。
教員にとって、ベストな妊娠時期はあるのでしょうか?
タイミングは気にしなくていい
「いつ妊娠すれば迷惑がかからないか」と考えてしまう方も多いですが、「子供が欲しい」とあなたが思った時がベストタイミングです。
仕事が忙しいから先延ばし…としていると、欲しいと思ったときに出来なかったということも十分考えられます。




6組に1組の夫婦が不妊に悩んでいると言われているよ…
その時、「もっと早くから考えておけばよかった…」と後悔しては遅いです。
仕事の代わりはいくらでもいるけど、あなた自身の代わりはいないですからね。
それでも、現場の混乱を最小限に抑えたいと考えるなら、次のようなタイミングが参考になります。
- 学年末〜年度初め(3〜4月)
- 長期休暇中(夏休み・冬休み)
長期休暇中だと先生同士の引継ぎもスムーズに行えると思います。
ただし、妊娠は計画通りにいくとは限らないもの。あくまで「目安」として考え、最終的には健康と家庭の事情を優先することが大切です。
妊娠がわかったら?報告のタイミングと順番
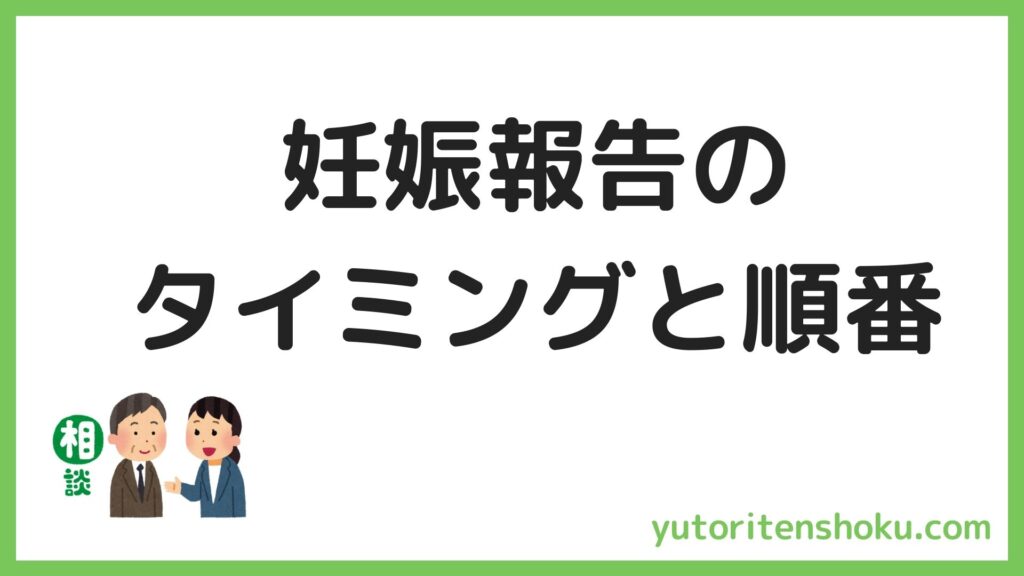
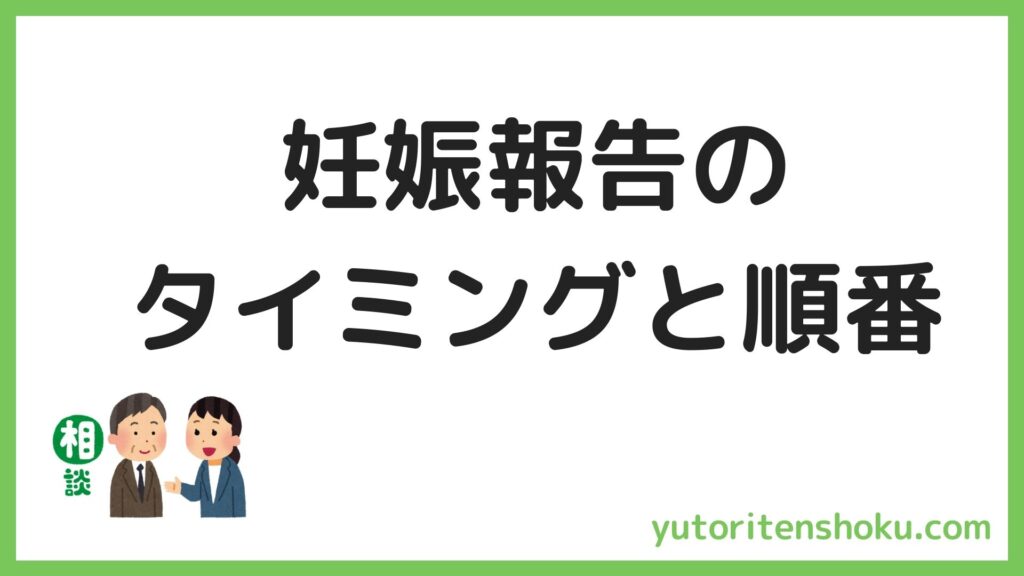
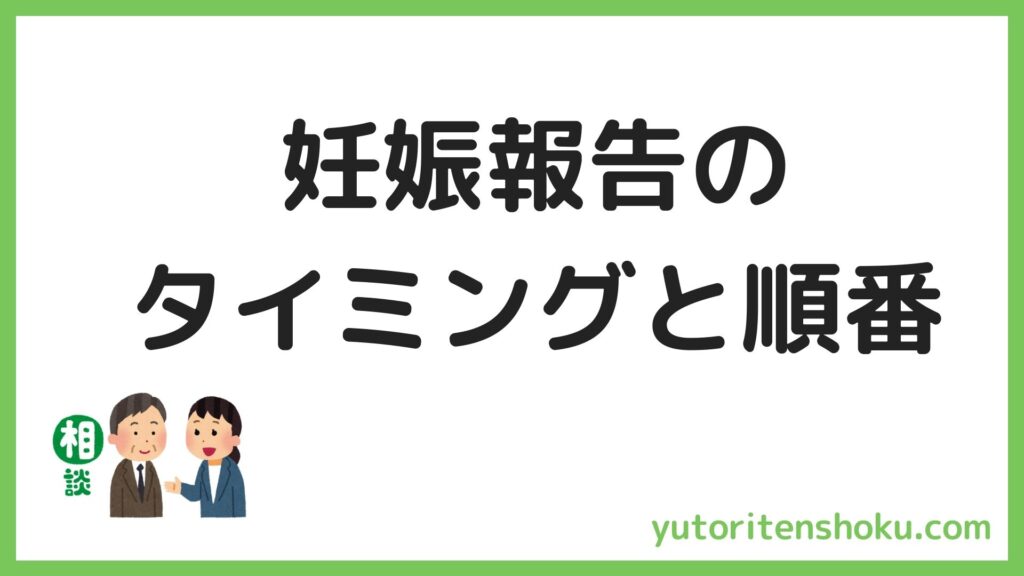
もし、妊娠していることが判明したらどうすればよいのでしょうか?
報告のタイミングや順番を解説します。
誰に・いつ・どう伝えるか
まずは管理職に安定期に入ったら報告。
報告は管理職→同僚→生徒・保護者の順。
報告のタイミング
一般的には、安定期(妊娠5ヶ月〜6ヶ月)に入るころを目安に報告する方が多いです。
しかし、つわりなど体調に変化がある場合はもっと早めに伝えるのが望ましいでしょう。
管理職への報告方法
安定期に入るまでは流産の可能性も高いので、早くから伝えるのはなるべく避けたいところです。
しかし、つわりなどで仕事を休まざるを得ない場合は、早めに管理職に相談するほうがよいです。
同僚への報告方法
管理職への報告が終わったら、同僚の先生方にも報告しましょう。
先に仲の良い同僚に報告してしまい、噂で妊娠していることが管理職にバレてしまうことがないよう、順番をきちんと守りましょう。
生徒・保護者への報告方法
管理職に報告したときに、生徒や保護者への報告するタイミングが決まるでしょう。
口頭や手紙でお知らせすることになると思います。
クレーム対応|保護者からの「なぜ今?」にどう向き合うか
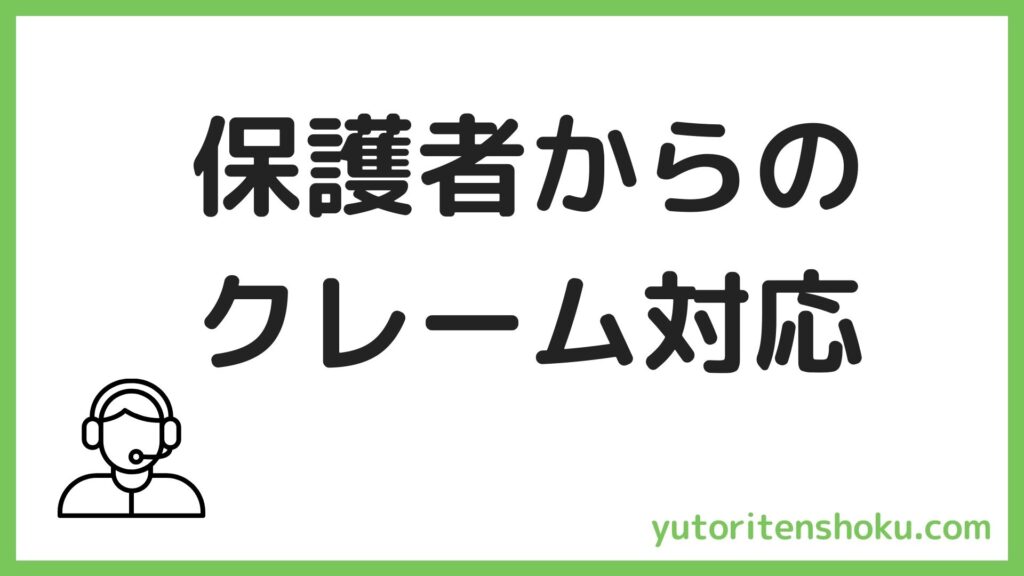
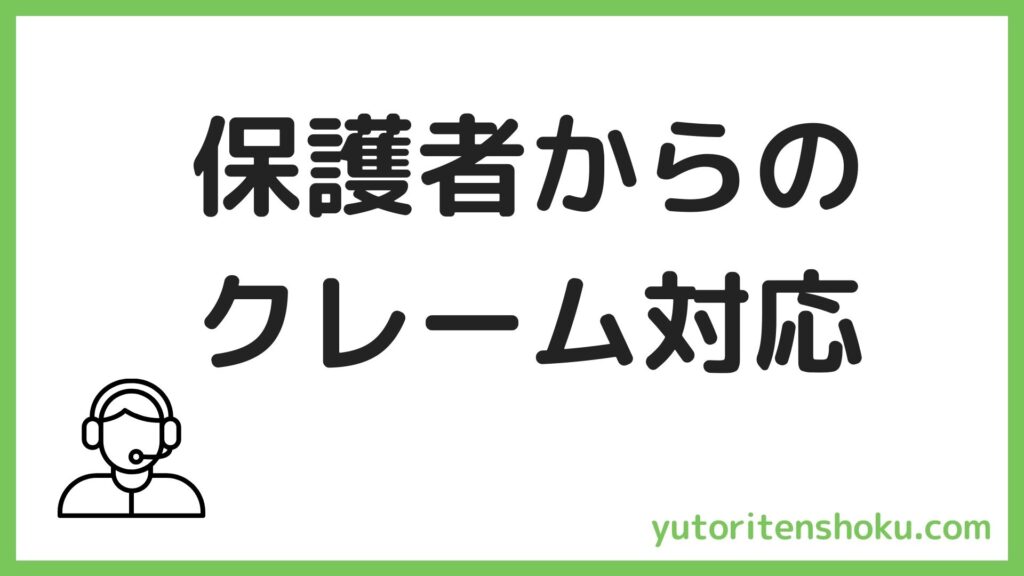
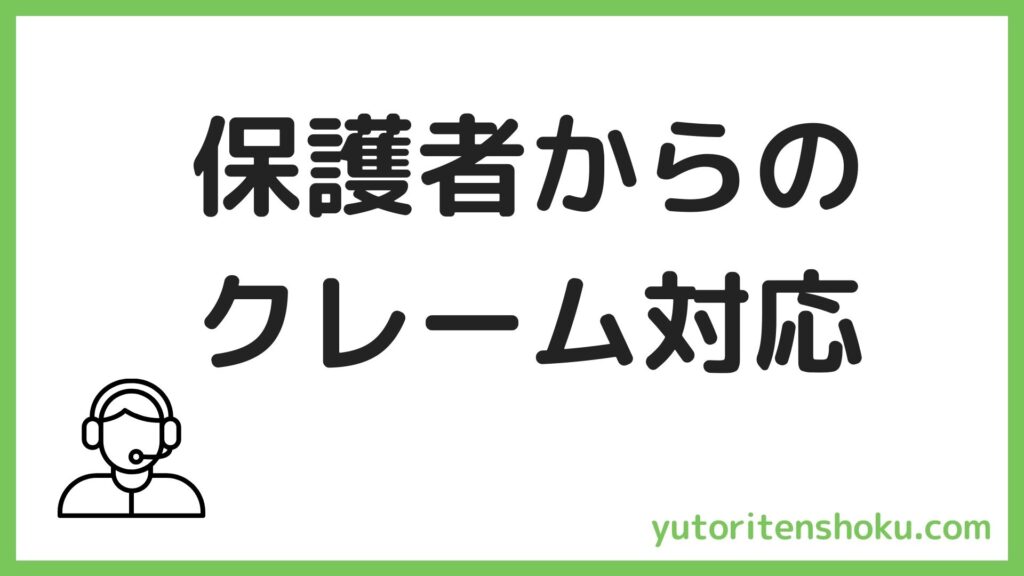
よくある声とその背景
このように、担任教員が妊娠・出産で途中退職や休暇に入ると、保護者から「なぜこの時期に?」「子どもが不安定にならないか心配」といったクレームが寄せられることがあります。
これは担任制度の構造上、子どもとの結びつきが強いため、変化に対する不安が出やすいことが背景にあります。
また、急な引き継ぎなどで混乱が起きると、学校全体への不信感にもつながりかねません。
クレームを受けた時の伝え方と対処法
妊娠報告をしたあとに、保護者からクレームが来たら、どんな対応を取ればよいのでしょうか?
まずは校長や教頭など、管理職が前面に出て対応することが原則です。
教員本人が一人で対応しようとすると、精神的負担が大きくなるので、絶対にやめましょう。
また、妊娠報告と同時に保護者向けの文書を用意し、引き継ぎ体制やサポート内容を丁寧に説明することで、理解を得やすくなります。
妊娠・出産と教職を両立するための工夫と選択肢
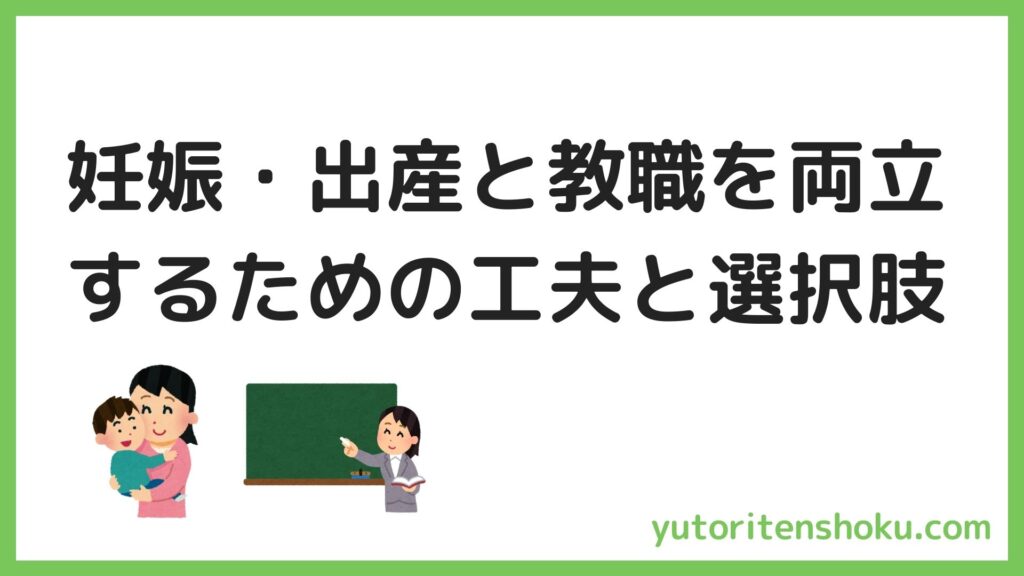
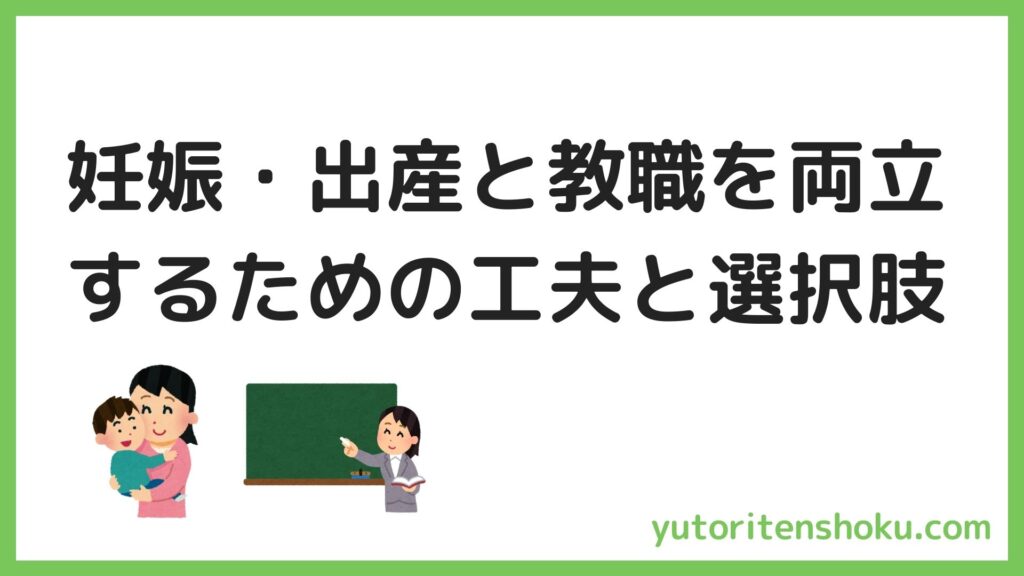
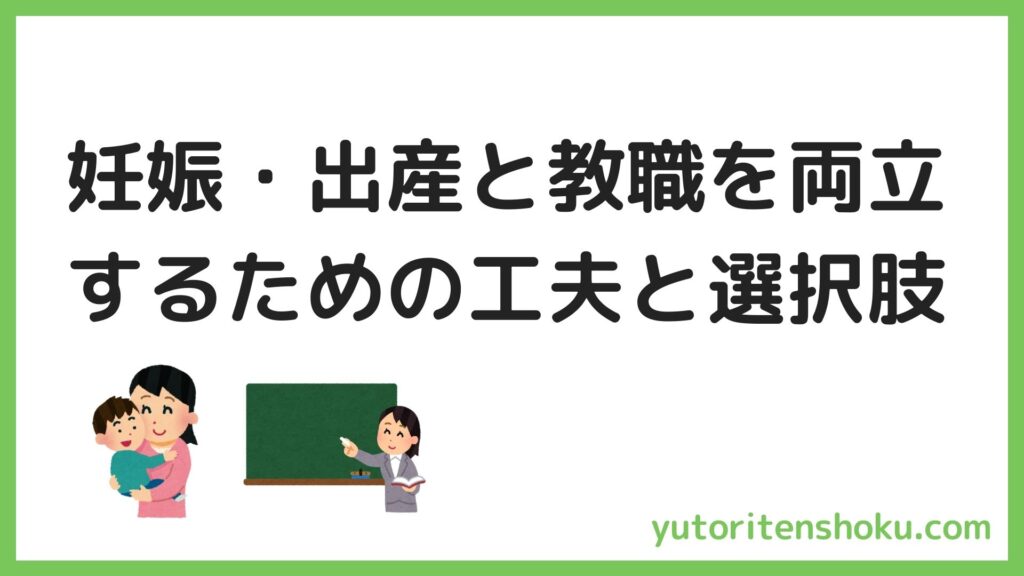
妊娠・出産と教師の仕事を両立することは、はっきり言って大変です。
少しでも負担を少なくするためにできる工夫や働き方の選択肢を紹介します。
無理なく働くための制度活用
妊娠中や育休から復帰した後に使える制度を活用して、無理なく働けるように工夫していきましょう。
教員が妊娠中・育児中に使える制度は以下の通りです。
【妊娠中】
- 妊産婦健康診断休暇
- 妊婦の通勤緩和
- 妊娠障害休暇
【育児中】
- 部分休業
- 育児短時間勤務
【条件】
妊娠中から出産後1年以内の間で、妊娠や出産、育児に関する医師の保健指導や健康診査を受ける場合に利用できる。
【日数等】
| 時期 | 利用できる回数 |
| 妊娠24週まで | 4週間に1回 |
| 妊娠25週から 36週まで | 2週間に1回 |
| 妊娠37週から 出産まで | 1週間に1回 |
| 出産後1年まで | その間に1回 |
通勤に利用する交通機関が混雑していて、母体や胎児に負担があるときは、出勤や退勤の時間を少し遅らせたり早めたりできる。(1日最大60分まで)
【条件】
妊娠が原因で体調が悪く、勤務困難なときに、病気休暇や産前休暇とは別に休暇を利用できる。
【日数等】
3週間以内
小学校入学前までの子どもを育てている人が対象で、1週間の労働時間を少なくできる制度。
月~金のうち働く日数や1日の働く時間を変えることができ、4つのパターンから選べる。
※詳しくはこちらのサイトをご覧ください。
どうしても難しい場合は転職という選択肢も
「制度はあっても使いにくい」「職場の理解が得られない」と感じた場合は、無理をせず転職も視野に入れましょう。
近年では、在宅勤務が可能な職業や、フレックスタイム制を採用している民間企業など、子育てと両立しやすい職場が増えています。
教職にこだわらず、自分と家族にとってよりよい働き方を模索することも、賢い選択の一つです。
▼転職についてもっと知りたい方はこちら▼
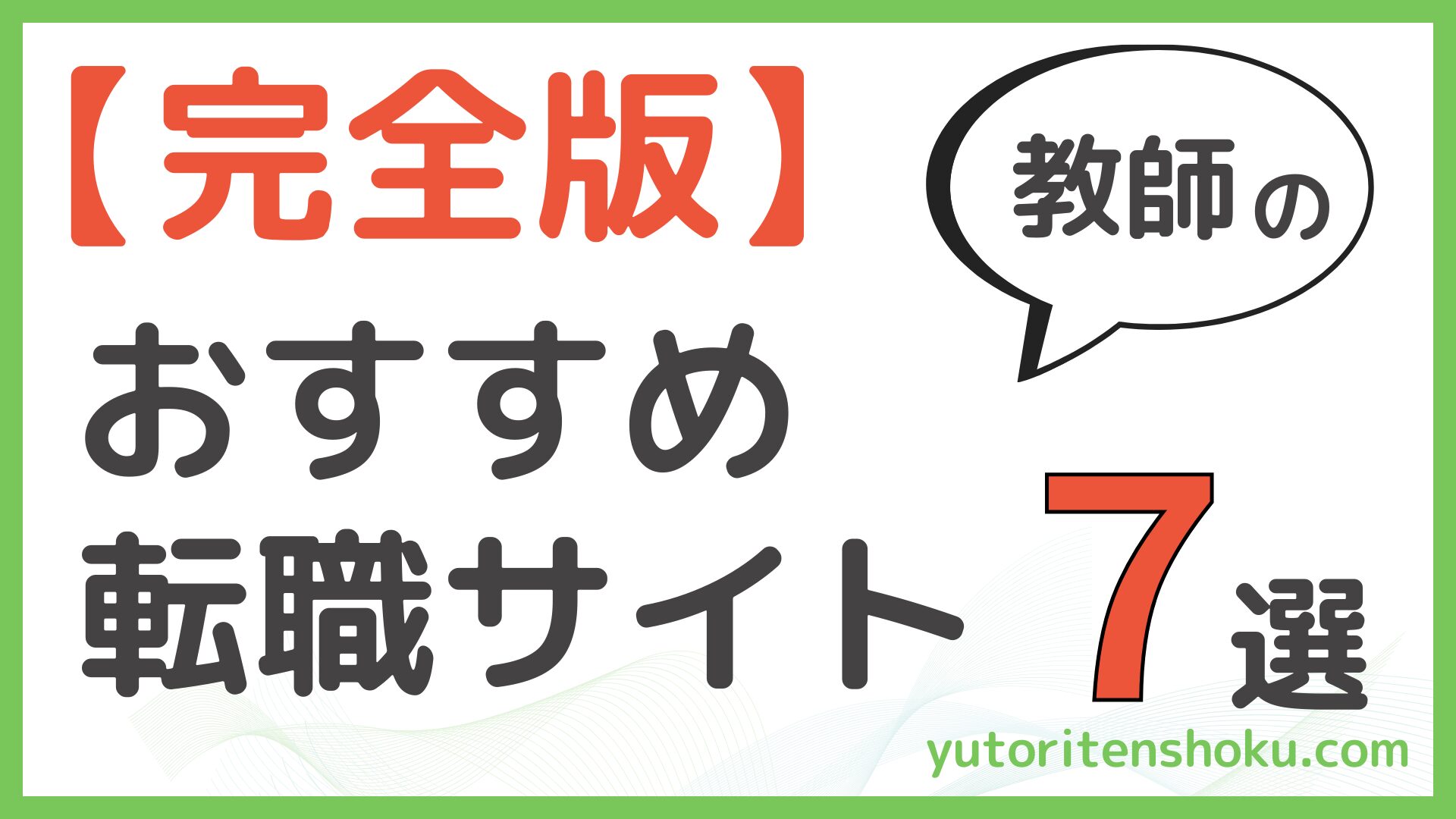
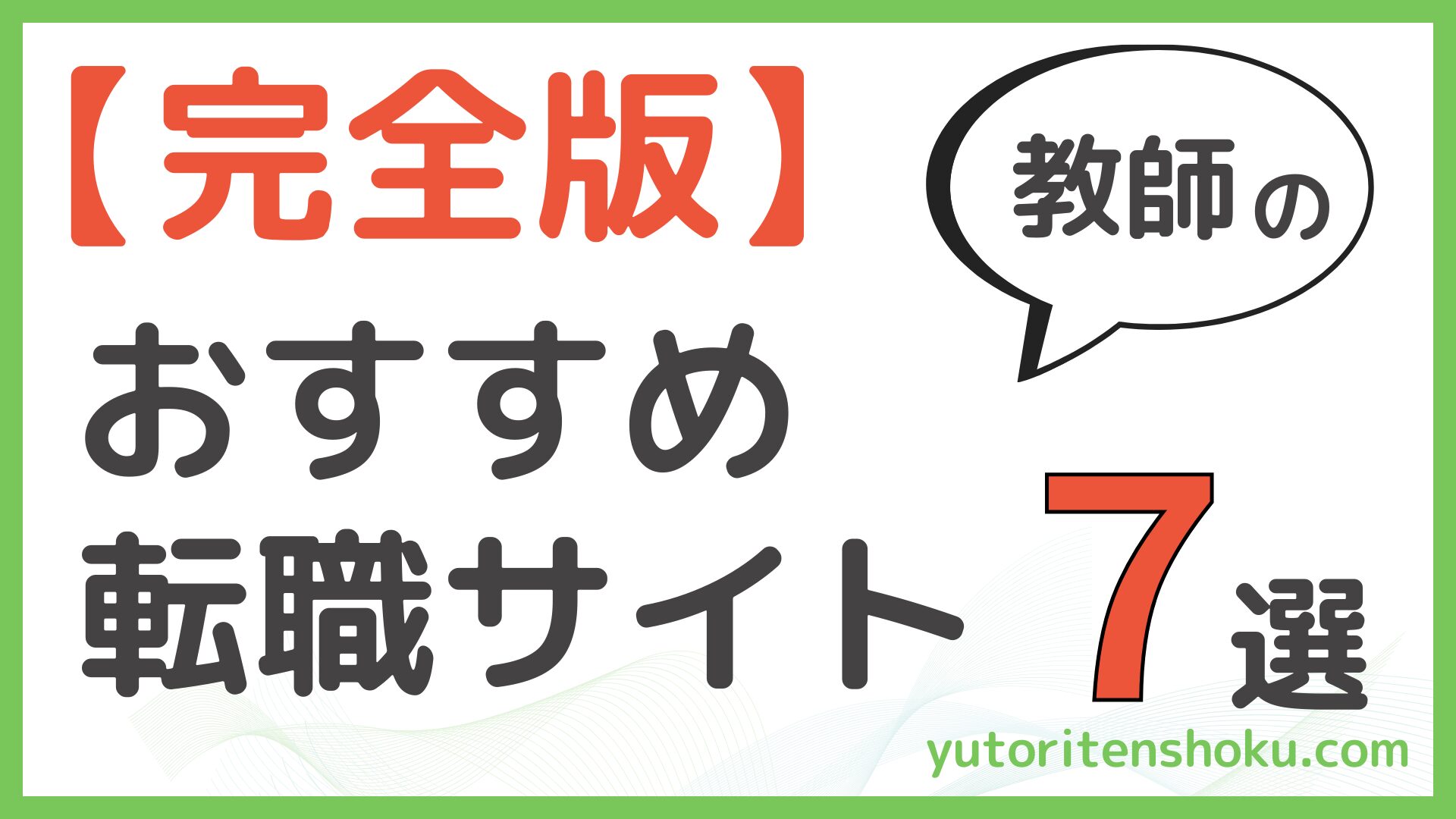
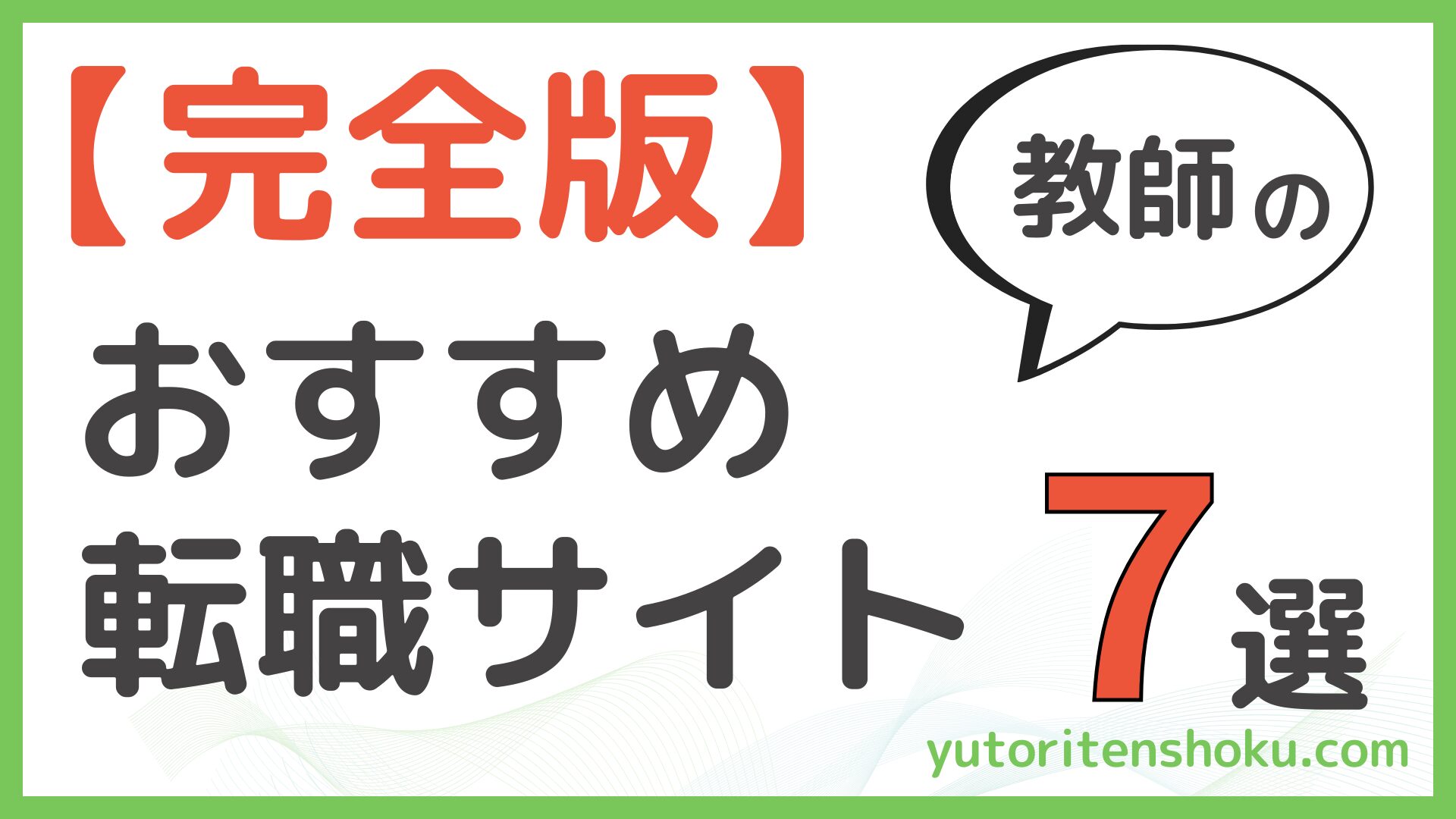
まとめ
妊娠や出産は、人生における大切な選択です。教職に就いているからといって、その選択を否定されたり、我慢を強いられたりする社会であってはなりません。
制度があっても使えない現実、職場の無理解、保護者対応への不安——それらをひとつひとつ乗り越えていくには、個人の努力だけでは限界があります。職場全体の理解と制度の見直しが必要です。
そのためには、まず現状を正しく知り、自分の人生にとってベストな選択肢を見極めていくことが大切です。
この記事が妊娠したいと思っている教員の方の少しでも参考になれば嬉しいです。