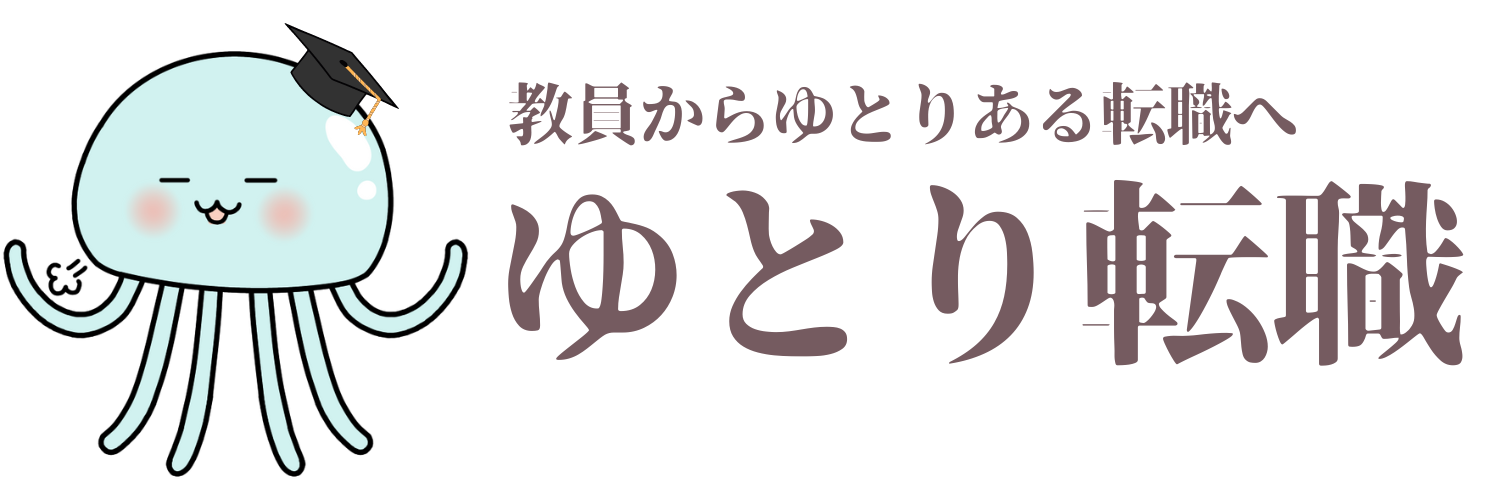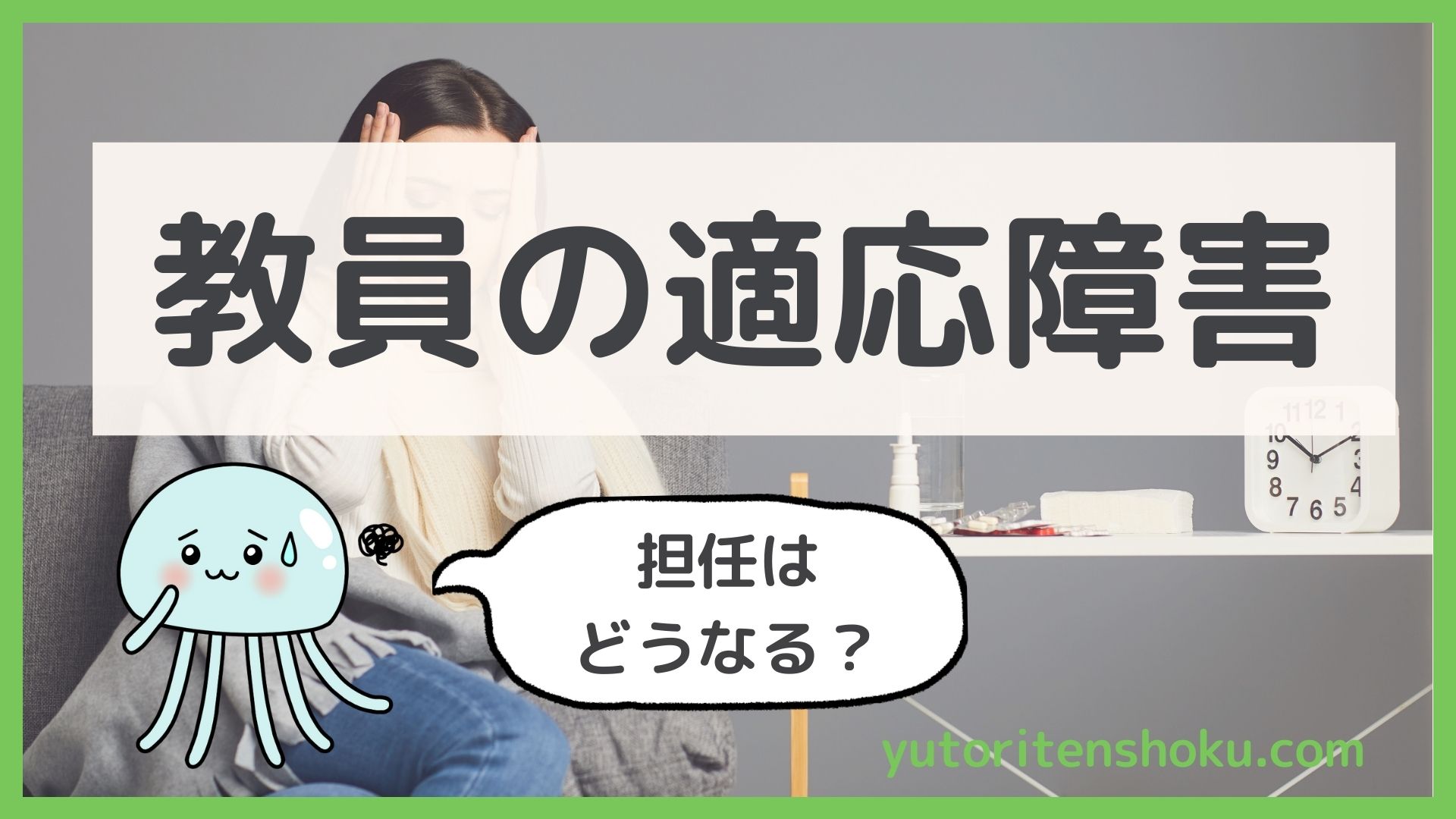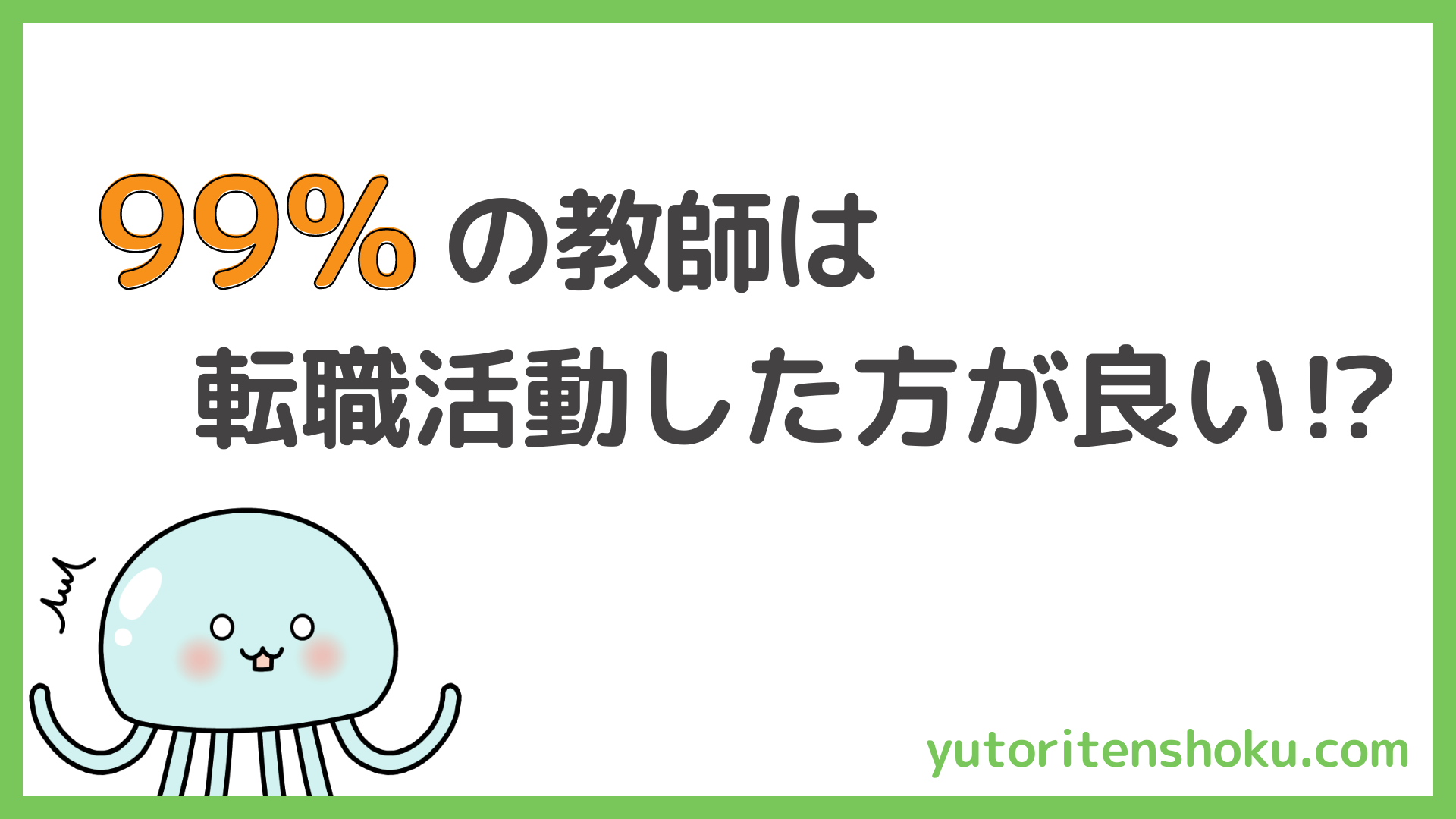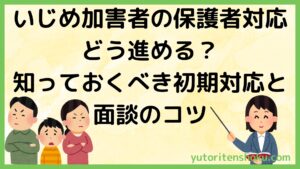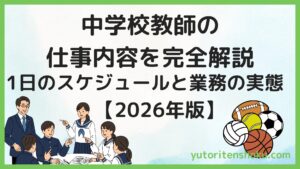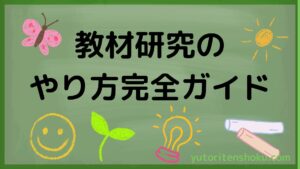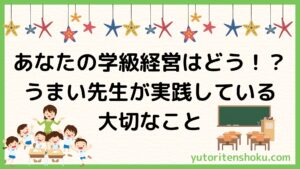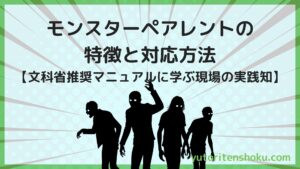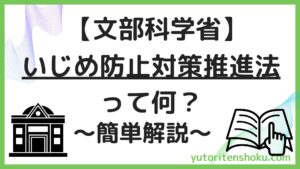ゆとり
ゆとり担任なのに適応障害になった…
どうしよう…




適応障害と診断されたけど、これからどうなるの?
教員として働く皆さんの中にも、適応障害と診断され、今後の働き方や現在の担任業務などはどうなるのだろうと不安に思っている人はいませんか?
文部科学省によると、令和5年度に精神疾患で休職した公立学校教職員は7,119人に上ると報告されています。
教員の仕事は業務量も膨大で、人間関係のストレスも多く、精神的な負荷がかかりやすい職業です。
実際、私も教員として働いていた時、いろいろなストレスが重なり、精神的に不安定になったことも多くありました。
いざ適応障害と診断されると、今後の仕事や自分の体がどうなるのか不安が募りますよね。
そこで今回は、適応障害と診断されたら、担任業務はどうなるのか?休職手続きや実際に適応障害になった教員の体験談なども踏まえて、今からできることを解説していきます。
- 適応障害とは?
- 担任業務はどうなる?
- 休職の手続きは?
- 適応障害になった教員の体験談
- 今自分にできることは?
適応障害とは?教員に多い理由
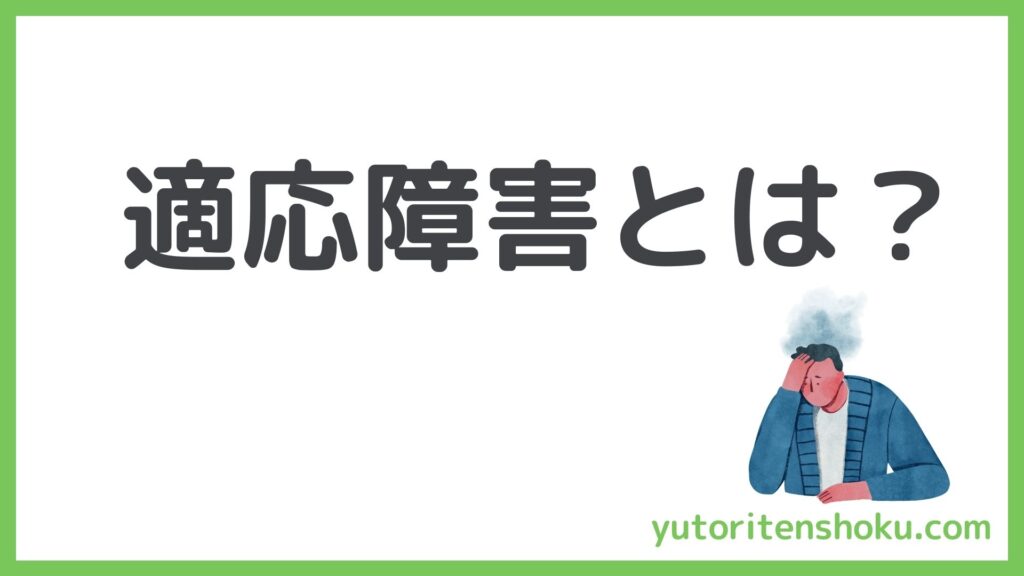
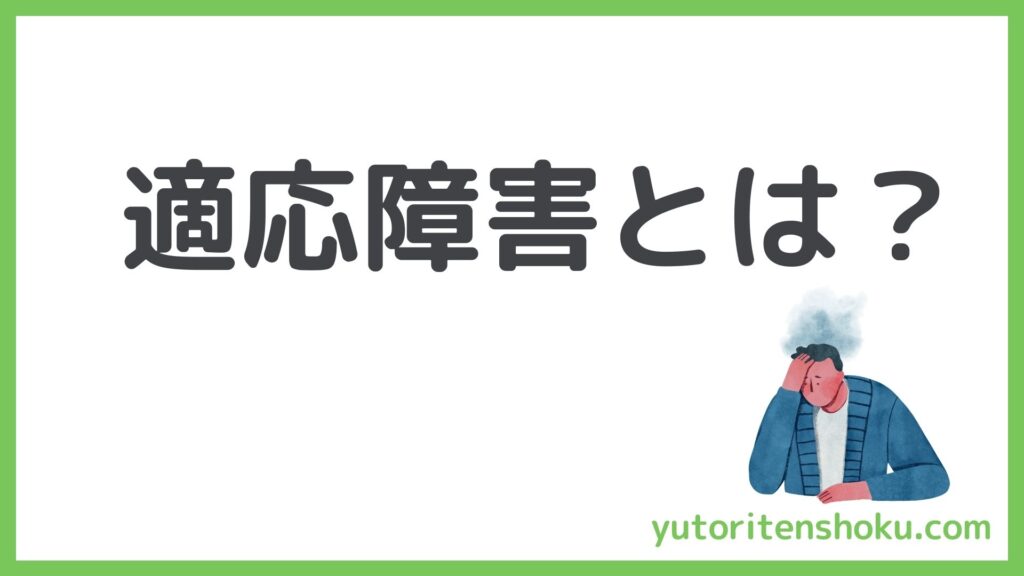
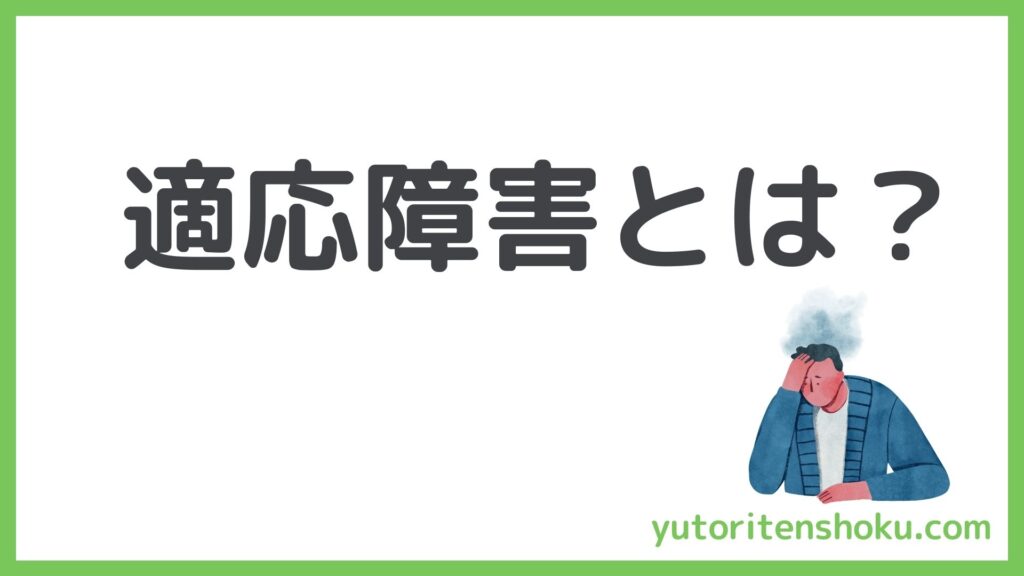
適応障害とは?
適応障害とは、ライフスタイルの変化や環境に馴染めず、ストレスとなって生活に影響をもたら精神障害のこと。
原因
適応障害の特徴的なポイントは「はっきりしたストレスの原因がある」ということです。
(例)
- 職場での人間関係(上司や同僚とのトラブル)
- 仕事の急な異動・環境の変化
- 担任になってプレッシャーを感じる
- 家族の介護や看病
- 異動など生活環境の変化
特に真面目で責任感が強い人ほど、ストレスを我慢しがちで、適応障害になりやすいと言われています。
症状
適応障害の症状は、精神的な症状と身体的な症状の両方があります。
【精神的な症状】
- 気分が落ち込む(うつ状態)
- 不安や焦りが強い
- イライラしやすくなる
- 泣いてしまうことが増える
- 仕事や学校に行けなくなる
- 自分を責める、無力感を感じる
【身体的な症状】
- 頭痛・めまい・腹痛など
- 不眠(寝つけない、夜中に目が覚める)
- 食欲不振または過食
- 疲れが取れない、だるさが続く




症状を放っておくと、「うつ病」に進行する可能性あり!
▼あわせて読みたい▼
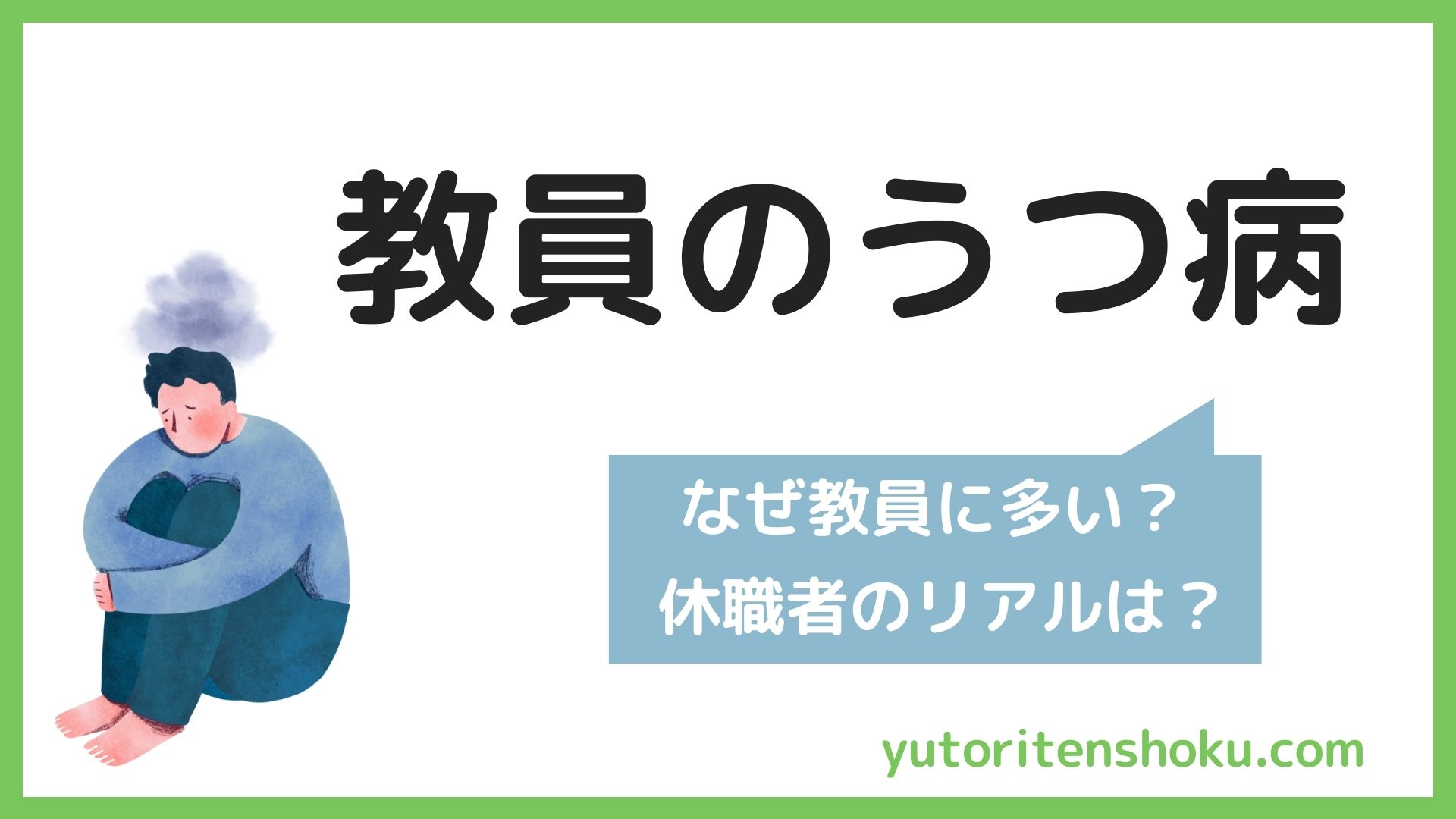
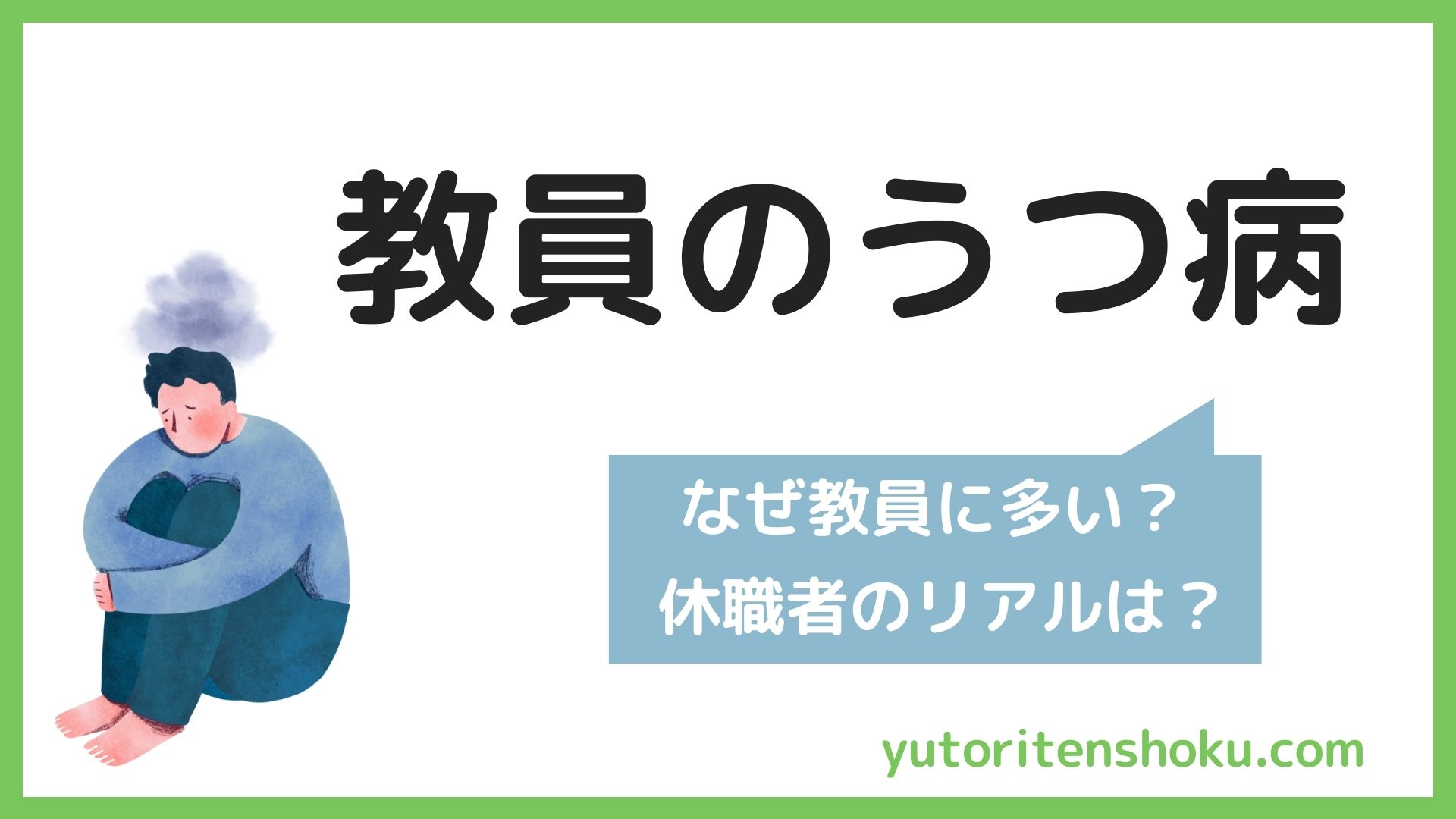
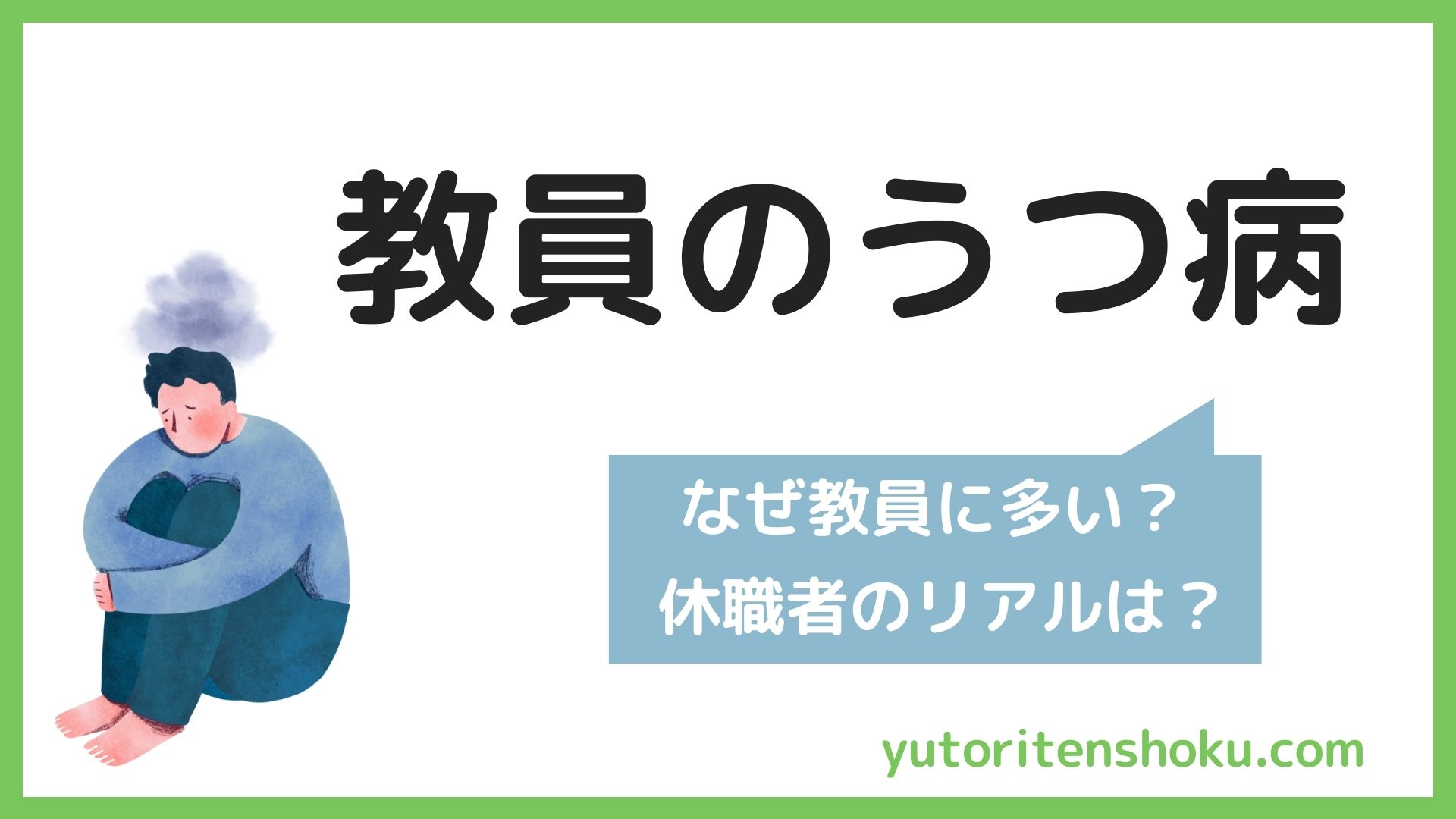
なぜ教員は適応障害になりやすいのか?
教員は適応障害になる人が多いと言われています。その理由はなぜなのでしょうか?
【主な理由】
- 業務量の多さとマルチタスク
- 「正解のない仕事」による精神的負担
- 教員は「真面目で頑張り屋」が多い
教員の仕事は、授業以外にも保護者対応や学校行事の運営、生徒指導などたくさんの仕事があります。
それに加え、生徒同士のトラブルや学力向上のための授業法、保護者との関わり方には正解がありません。
特に担任を持つと、「自分ひとりでやらなければならない」という想像以上のプレッシャーがかかります。
真面目で頑張り屋が多い教員はこれらのことが積み重なって、「心の疲れ」が出てきてしまい、適応障害になりやすいのではないかと言われています。




私のいた学校にも適応障害を経験した先生は数人いたよ
適応障害になったら担任業務はどうなる?
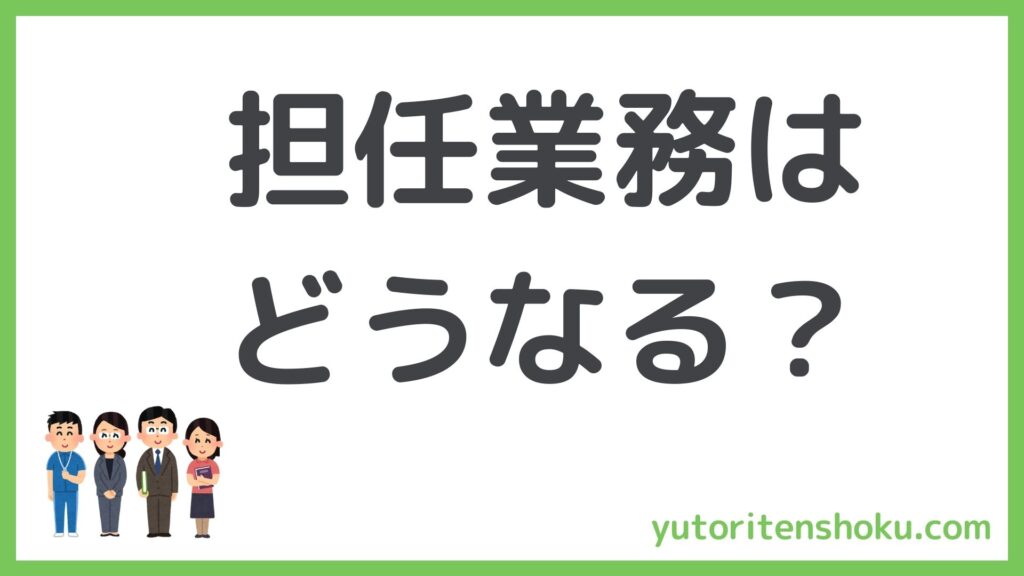
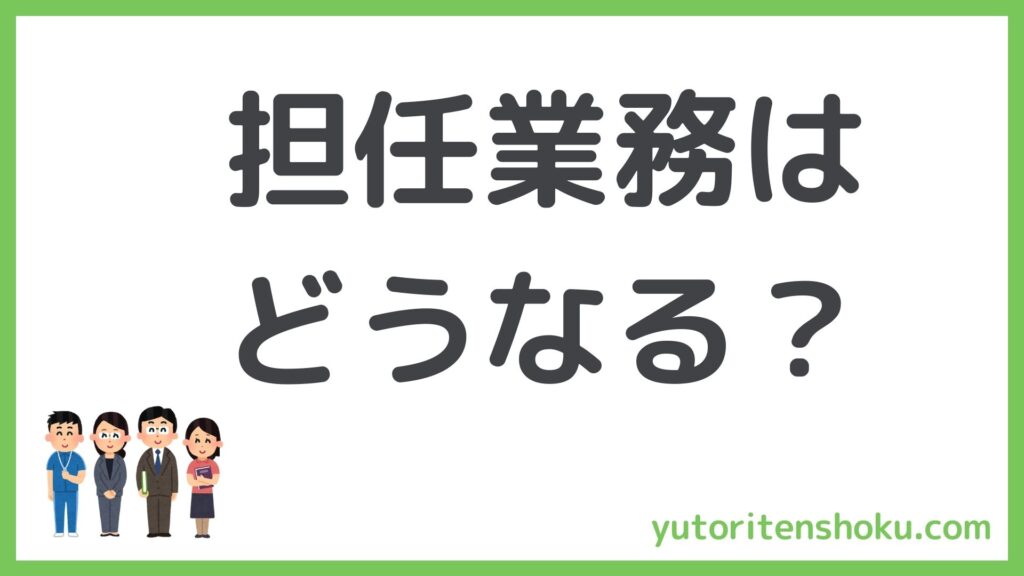
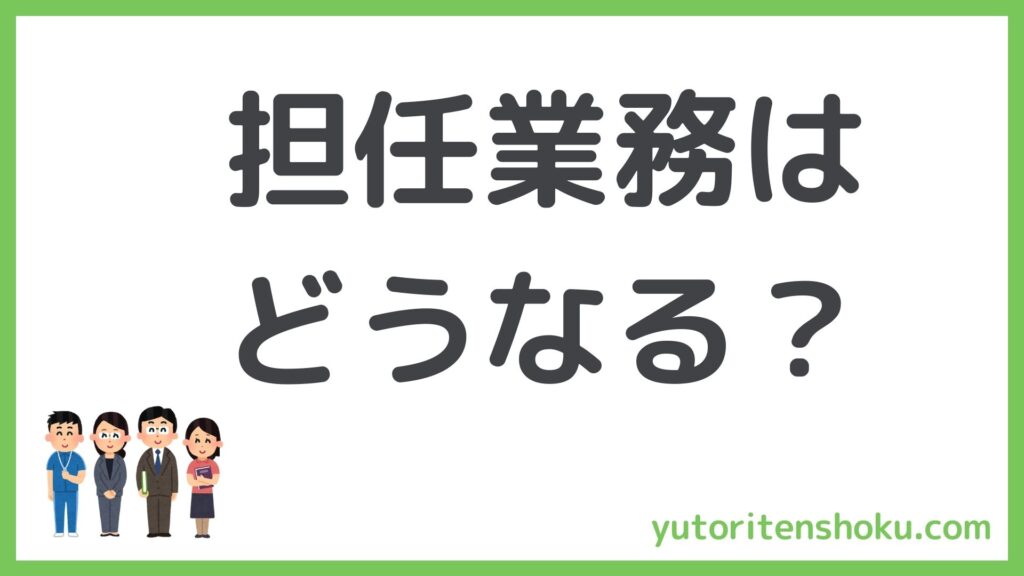
担任を持っている状態で「適応障害」と診断されたら、「クラスはどうなるの?」「自分が抜けたら迷惑をかけない?」など不安を抱える先生は少なくありません。
ここでは、診断後の担任業務や何を優先すべきかについて解説します。
担任は途中で辞めてもいい




途中で担任を放り出すなんて申し訳ない…
こんな罪悪感を感じてしまう先生は少なくありません。
しかし、適応障害と診断されたということは「心が限界を迎えたサイン」なのです。
無理に続けていたら、うつ病にだって悪化しかねません。
“今は無理をしないこと”が、未来の自分を守るために最も必要な選択です。
担任業務は、誰かが引き継いでくれる
担任が休職した場合、学校は代わりの体制を整える責任があります。
- 臨時講師が担任を引き継ぐ
- 学年チームで分担して対応
- 生徒・保護者にも状況を伝え、学校全体でフォロー
「自分がいなければクラスが回らない」なんてことはありません。
あなた一人が背負わなくても、職場全体で子どもたちを見守る体制が整うはずです。




自分の代わりはいくらでもいるよ!
まずは、休むことが最優先
クラスや仕事のことも大事ですが、何よりも一番大事なのは、あなた自身の心と体の健康です。
- 疲れてるのに無理して出勤する
- 頭はぼーっとしてるのに、笑顔で対応する
- 家に帰っても、眠れず明日のことを考え続ける
そんな状態が続いたら、きっとどこかで限界がきてしまいます。
だからこそ、「いったん休む」という選択は、自分を守るために必要な行動なんです。




自分の心と体を守ることが一番大事!
担任を離れても、復帰の道はある
一度担任を離れたからといって、「戻れなくなる」わけではありません。
- 復帰後は副担任や教科担当からスタート
- 段階的な勤務で少しずつ職場に慣れていける
- 医師や職場と相談しながら無理のない復帰計画が立てられる
実際、多くの先生方も休職後、段階的に現場に戻ってきています。
休んだことがマイナス評価になることは基本的にありません。
それよりも、自分を見つめ直し、心身を整えてまた働ける状態になることのほうが大事です。




心配無用だよ!
教師自身が元気でなければ、子供たちにもそれが伝わります。
まずは、自分のためにも子供のためにも、「一度休んでみる」ことをおススメします。
休職したい場合はどうすればいい?
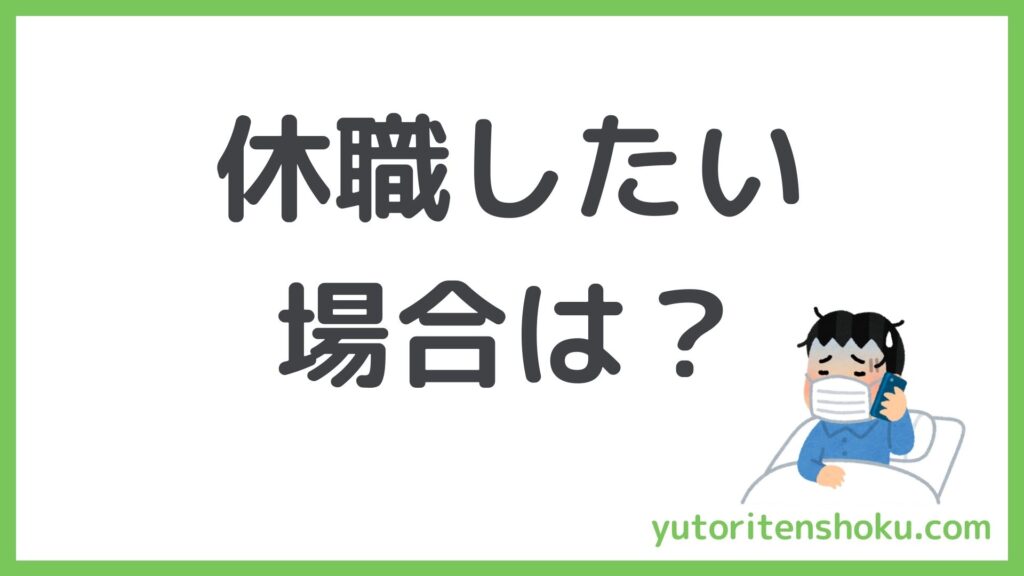
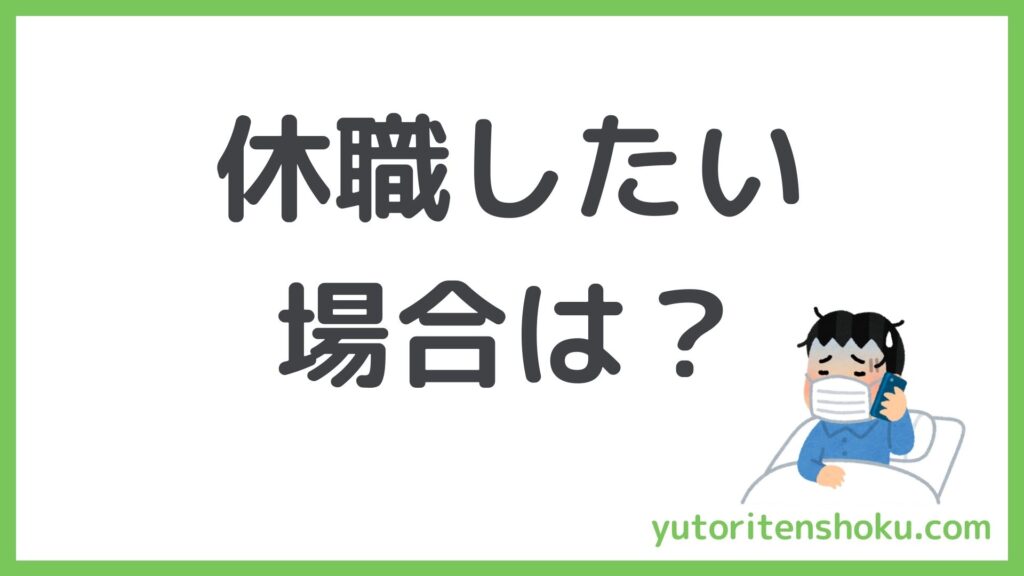
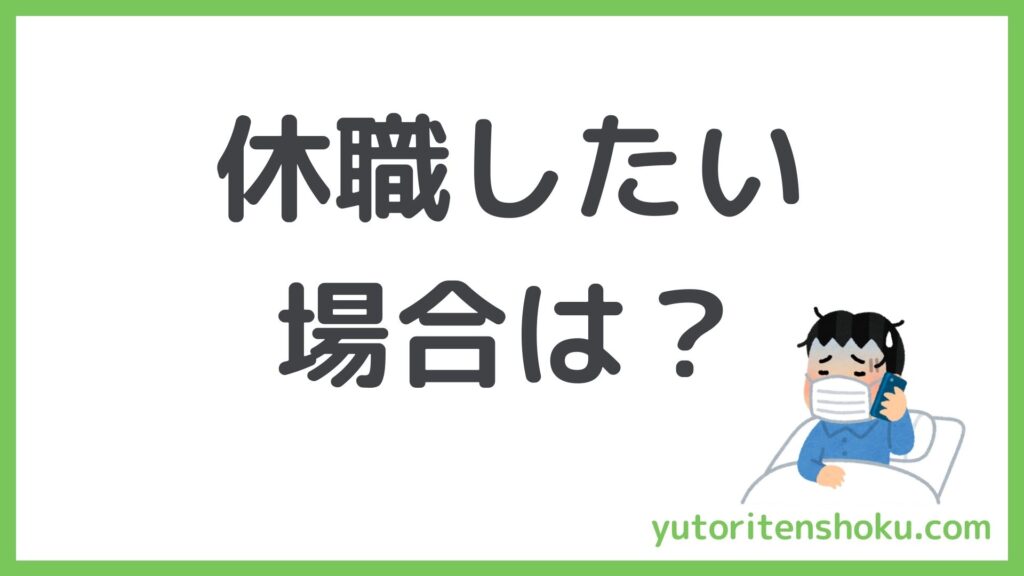
適応障害と診断され、一度仕事をお休みしたい場合、どのような手続きを取ればよいのでしょうか?
病気休暇の取得方法について
体や心が不調になってから病気休暇を取得するまでの流れをまとめました。
精神的な疲れや不安が続いて、休職しようか悩んでいる人は参考にしてください。
「しんどいな」と感じたら、まずは医療機関で診察を受けましょう。
適応障害と診断されれば、「一定期間の休養が必要」などと書かれた診断書を発行してもらえます。
※この診断書が、休職の申請に必須になります。
診断書が出たら、職場(主に校長または教頭)に相談しましょう。
休暇取ると決まったら、診断書を学校に提出しましょう。
休暇が決まったら、ゆっくり心と体を休めましょう。
休暇期間が終わったら、いよいよ復職です。
管理職と相談しながら、無理のない範囲で学校現場に戻りましょう。
病気休暇の期間内に回復できなかった場合、病気休職というのを取得できます。
その際、休職願や医師の診断書を提出する必要があります。
病気休暇中のお給料は?
病気休暇中のお給料のこと、気になりますよね。
果たして、金銭面はどうなるのでしょうか?
病気休暇中、最大90日間(自治体によっては180日間)お給料は変わらず、全額支給となります。




全額支給だなんて驚き!!
▼病気休暇について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください▼
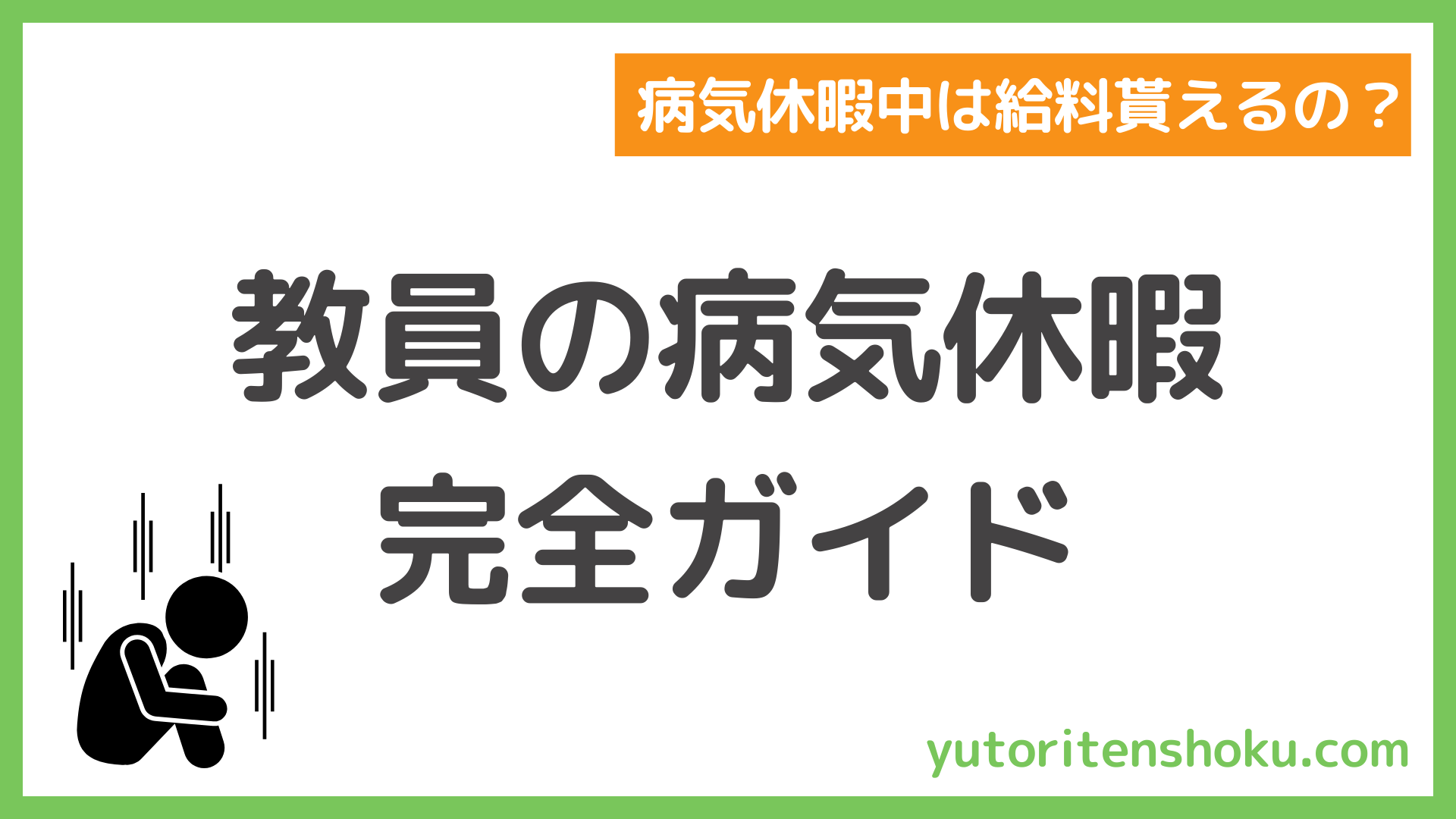
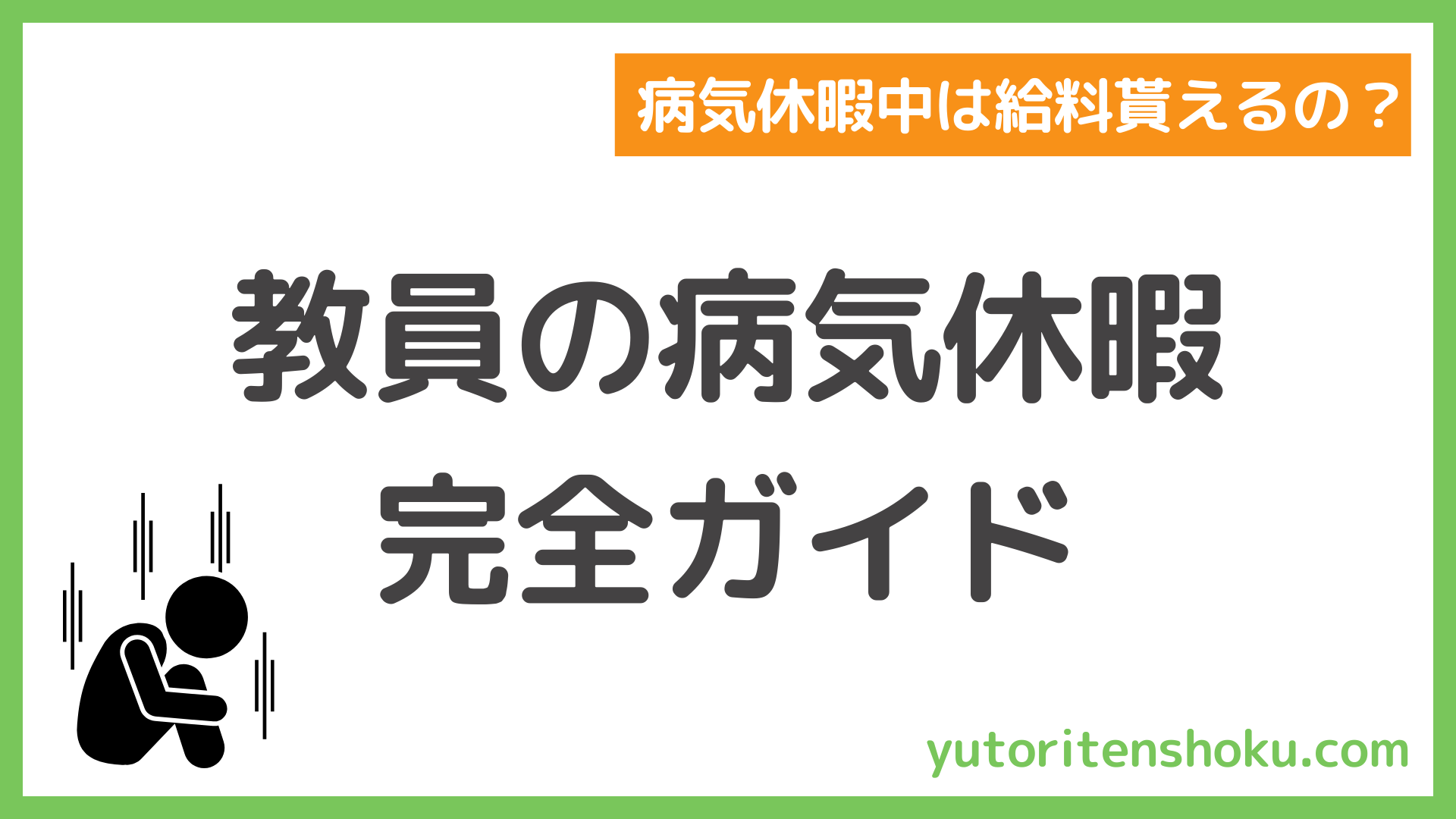
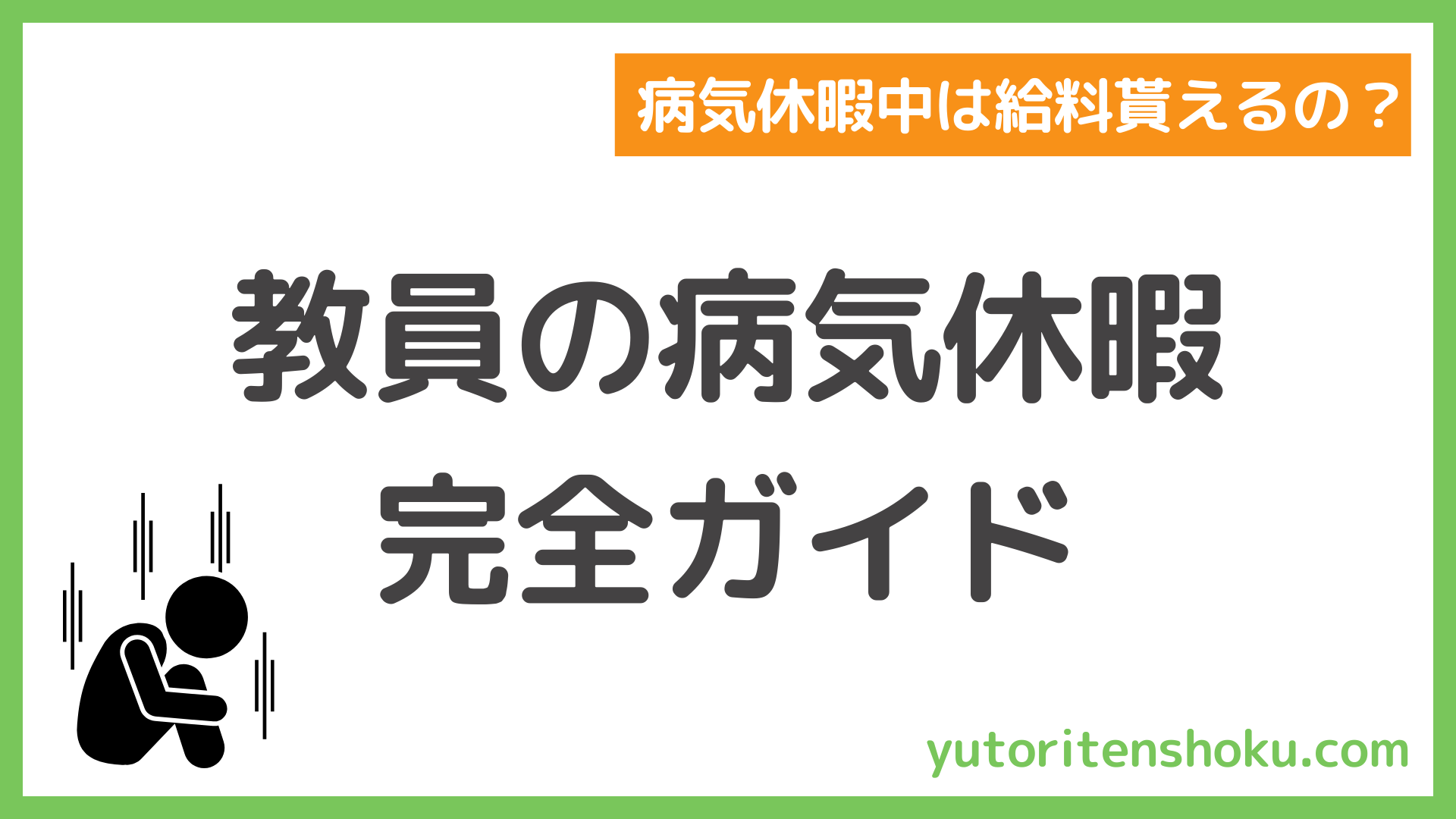
適応障害になった教員の体験談
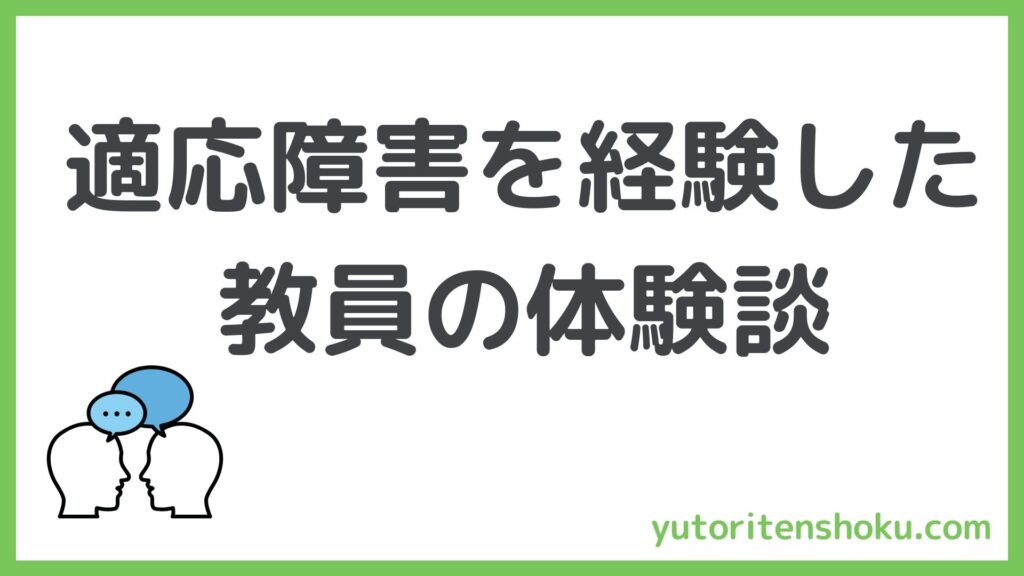
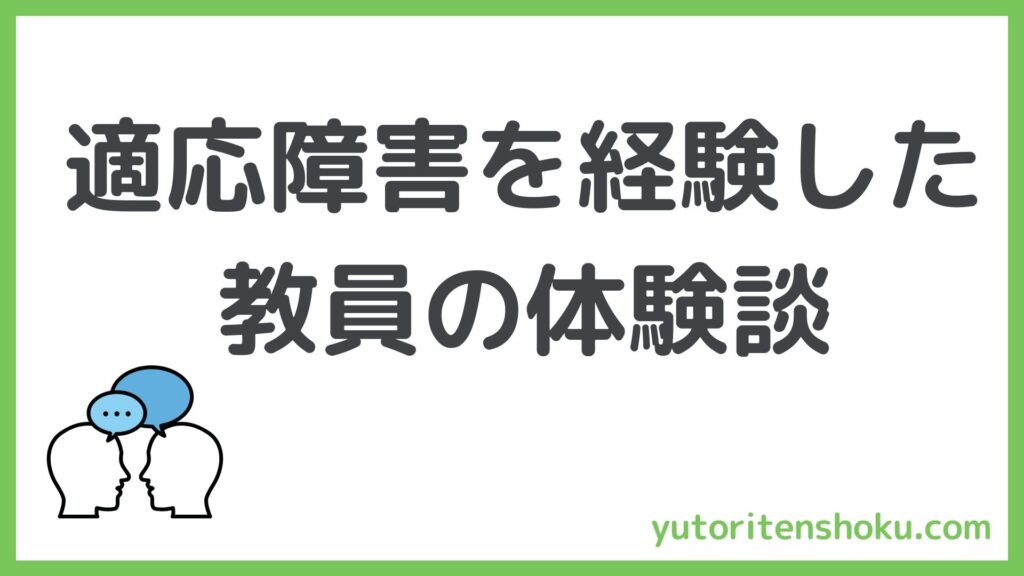
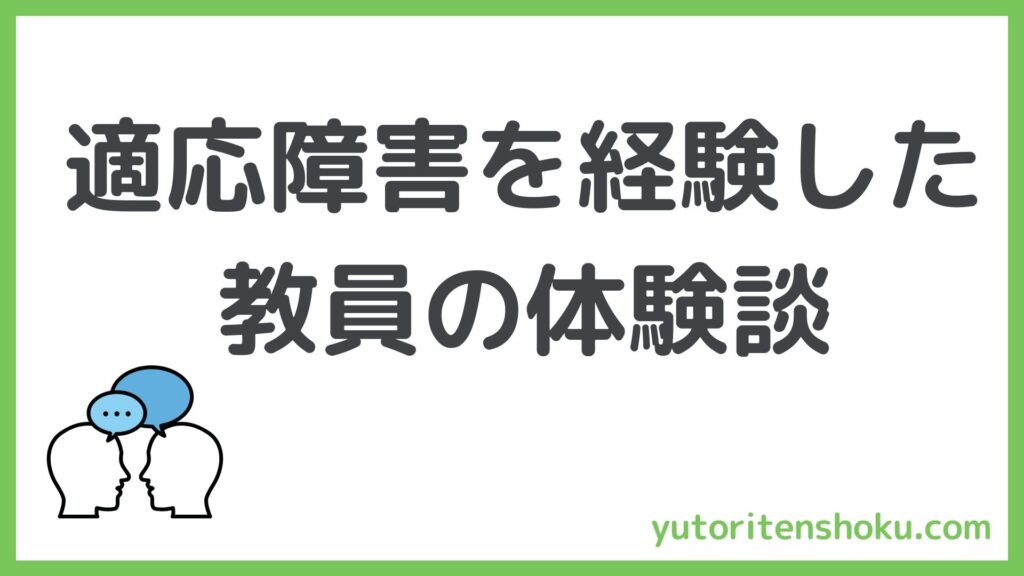
実際に適応障害になり、仕事をお休みしたり復職したりした経験をもつ教員の体験談をご紹介します。
みなさんも自分の状況と重ねて共感したり、いろいろな考え方に触れてみたりしてください。




過去・現在・未来の自分を想像しながら読んでみてね
【体験談①】適応障害になるまでの具体的な状況
【体験談②】適応障害と診断され、休職したとき
【体験談③】復職したときの状況
適応障害になったあなたが今できること
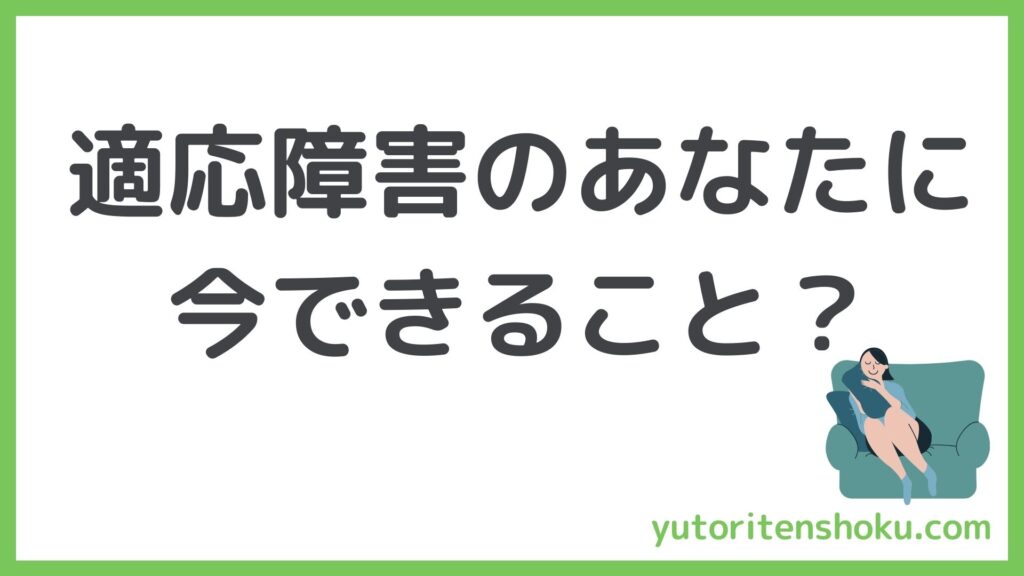
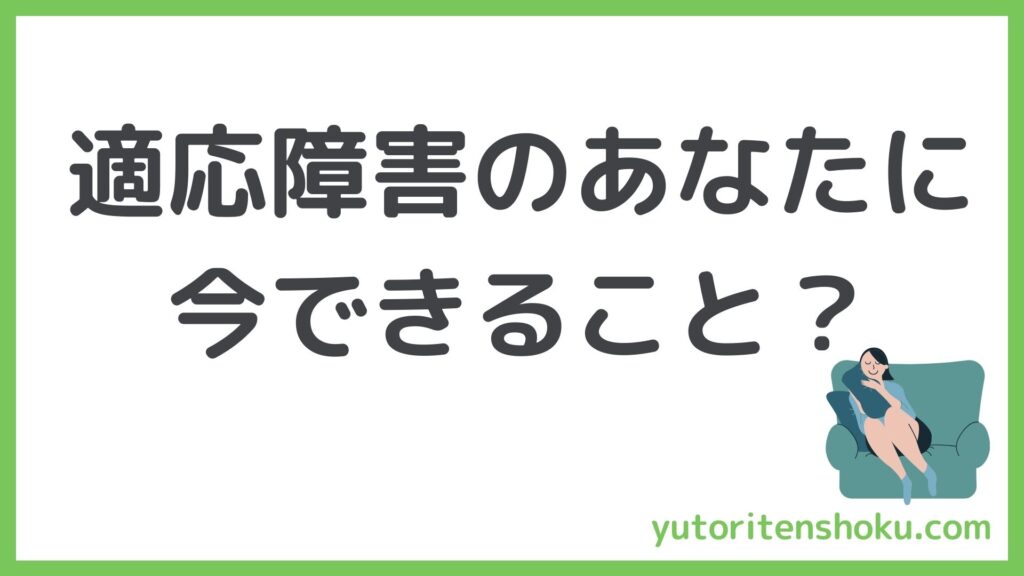
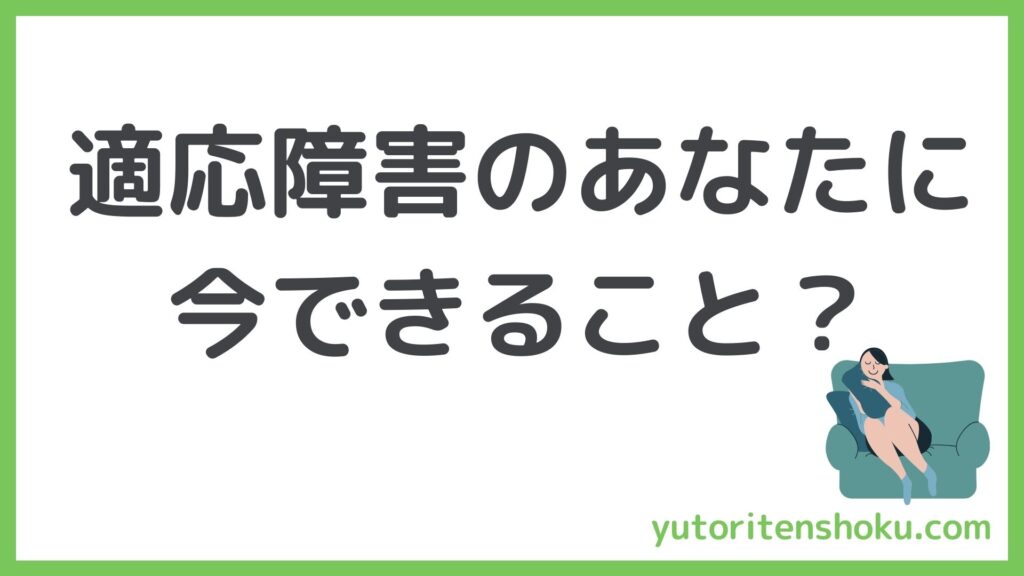
まずは「自分のつらさを認める」
適応障害と診断されても、「自分が甘えているだけかも」「こんなことで休んでいいのかな」と感じる人は多いです。
でも、それは違います。
心や体が悲鳴をあげているのに、“頑張らなきゃ”と自分を追い込んでしまうことの方が危険なんです。
まずは、今の自分の状態を否定せずに「よくがんばってきた」と、自分自身を労わってあげてください。




自分のことをいっぱい褒めよう
しっかり休むことを最優先にする
今は、何よりも休養が必要なときです。
無理に仕事を続けたり、家事をこなそうとせず、自分に「休む許可」を出すことがとても大切です。
自分の好きなことをしたり、今までやってみたかったことに挑戦するのも良し。
仕事のことを考えず、「休むことに集中」してみてください。
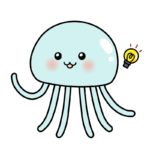
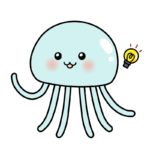
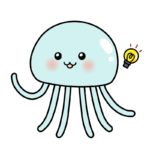
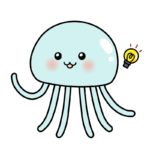
休むことも大事な仕事だよ
医師や周囲の人に相談する
ひとりで抱え込まずに、医師や信頼できる人に気持ちを話すことも、回復への大事な一歩です。
- 主治医に「どれくらい休めばいいのか」「仕事復帰はいつごろか」相談する
- 職場の管理職に、今後の働き方について相談する
- 家族や友人に「今ちょっとしんどい」と打ち明ける
言葉にするだけで、気持ちが軽くなることもあります。
「助けを求めるのが苦手」な人ほど、意識して声を出してみてください。




誰かに話すとスッキリするよ
情報を集めすぎないことも大切
「適応障害 治し方」「仕事 休む 迷惑」など、検索しすぎてしまうことってありませんか?
不安な気持ちがあると、ついネットに頼りがちになりますよね。
でも、情報が多すぎると、かえって不安が増すこともあります。
信頼できる情報源だけに絞って、必要以上に調べすぎないことも、心を守るひとつの方法です。




デジタルデトックスもいいね!
働き方を見直してみるのもひとつの選択肢
心や体が限界になった背景には、働き方や職場環境の問題があることも少なくありません。
- 担任ではなく教科担当・支援員として働く
- 非常勤や時短勤務など、負担を減らした形での勤務
- いったん教育現場から離れて、別の道を探す
「辞めるか続けるか」ではなく、「どう働くか」を見直すことが、これからの自分を守ることにもつながります。
焦らず、少しずつ「自分にとって心地いい働き方」を探していきましょう。
▼こちらの記事もおすすめ▼







いろいろな働き方を考えてみよう
まとめ
教員という仕事は、子どもや保護者、同僚…多くの人との関わりの中で、心をすり減らしやすい仕事です。
適応障害と診断されたことは「今のままでは限界です」という、心からのSOSです。
まずはゆっくり休んで、少し元気が出たら、「どうすれば自分が安心して生きられるか」をじっくり考えていきましょう。
あなた自身の心と体を、一番に守ってあげてください。